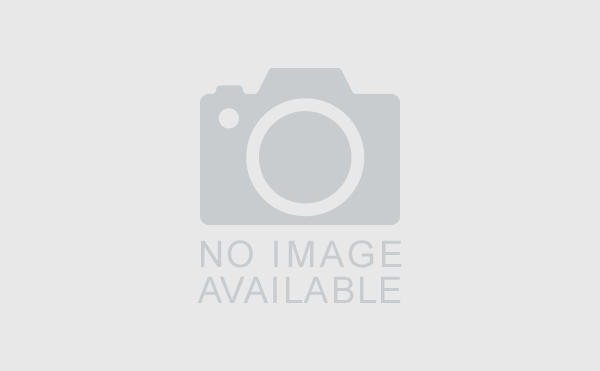賃金台帳とは?作成義務や記載項目、実務での注意点をわかりやすく解説
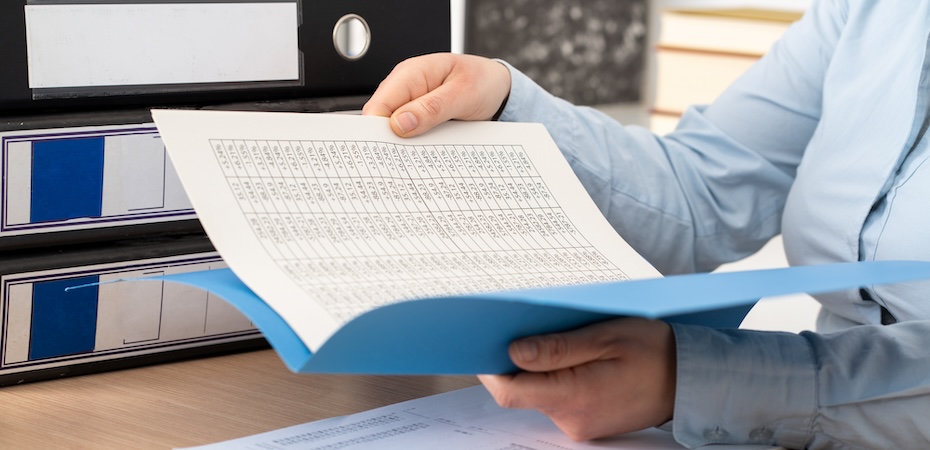
KEYWORDS 賃金台帳
企業が従業員を雇用する際に欠かせない「労務管理帳簿」。その中でも賃金台帳は、すべての事業場で作成・保存が義務付けられている法定帳簿であり、労働基準監督署の調査時には必ず提出を求められる重要な資料です。
しかし、人事部門で初めて労務管理を担当する方の中には、
「給与明細と何が違うの?」
「どの項目まで書けば法的に問題ないの?」
「電子化しても大丈夫?」
といった疑問を抱くケースが少なくありません。
本記事では、賃金台帳の基本から、具体的な記載項目、給与明細との違い、実務での注意点、さらに経営に役立つ活用方法までをわかりやすく解説していきます。人事・労務担当の方や、人事・労務の仕事に関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
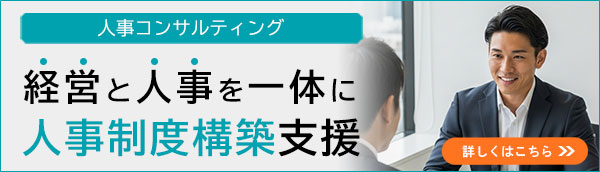
賃金台帳とは
「賃金台帳」とは、企業が従業員に支払った賃金の詳細を記録する帳簿のことを指し、働基準法第108条、労働基準法施行規則第54条に定められています。すべての事業場に作成・保存が義務付けられている法定帳簿のひとつで、労働者名簿や出勤簿と並んで「三大帳簿」と呼ばれることもあります。
主な目的は、労働者に適正な賃金が支払われているか、労働基準監督署が確認できるようにすることです。賃金台帳の保管期間は、労働基準法第109条によって5年間と定められています。以前は3年間でしたが、2020年4月の法改正によって3年から5年へと延長されました。
当面の間、保管期間は3年間に据え置かれていまが、あくまでも経過措置であるため、将来的には5年間の保管が必要となります。
賃金台帳の記載項目
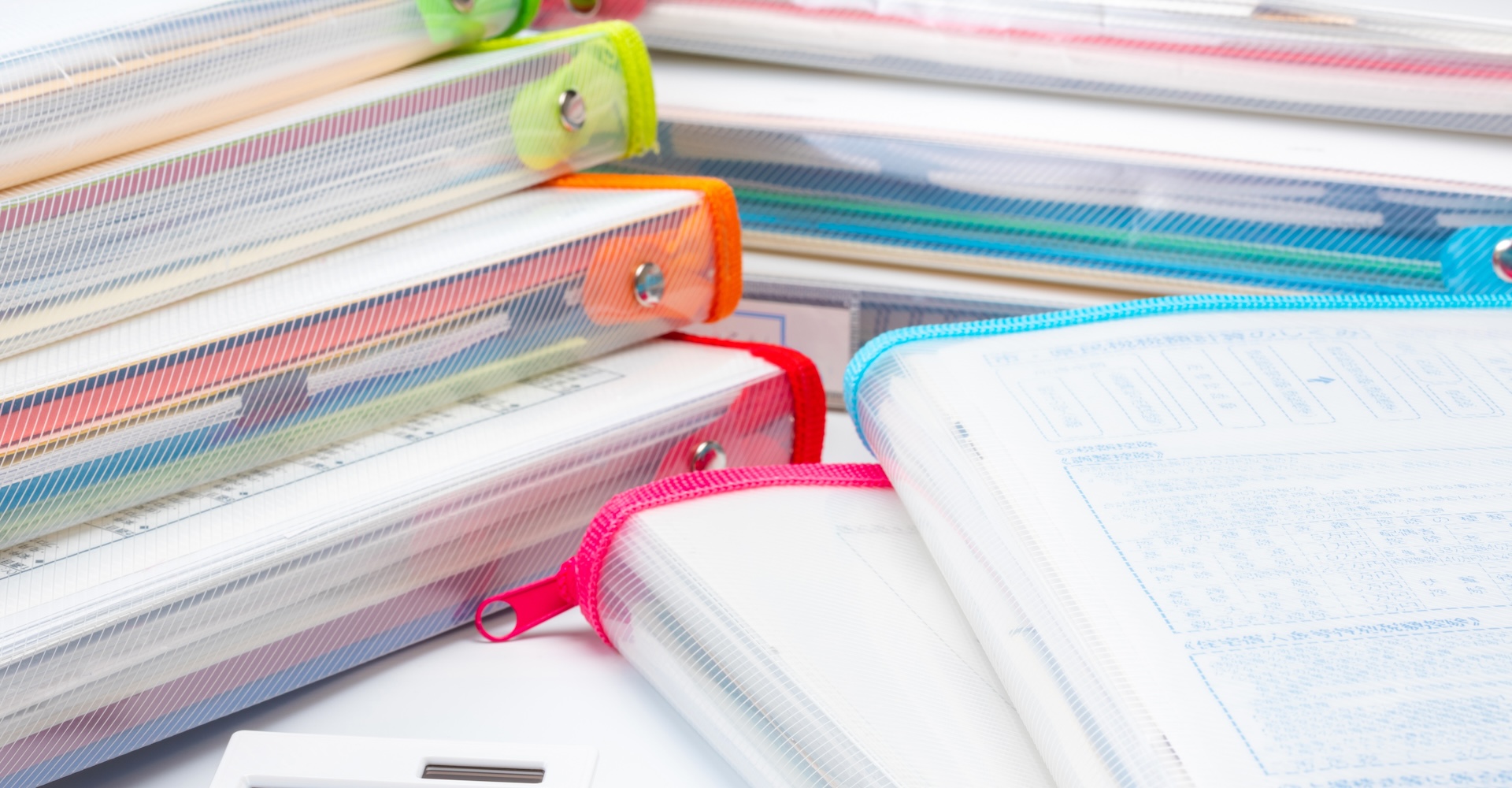
賃金台帳の必須記載項目は以下の通りです。記載内容は労働基準法施行規則第54条で厳粛に定められており、記載漏れがあると「不備」と判断され、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあります。
出勤簿やタイムカードなどと必ず突き合わせて、整合性を保つようにしてください。
| 項目 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 労働者氏名 | 住民票に登録してある正式な氏名を記載してください。 |
| 性別 | 従業員の性別を記載してください。 |
| 賃金計算期間 | 「1日~月末」など、賃金締切日と支払日を明確に記載してください |
| 労働日数 | 月間の出勤日数を記載します。欠勤・有給休暇・特別休暇を区分して記録しましょう。 |
| 労働時間数 | 所定労働時間+実労働時間を記載します。打刻記録と整合性があるか必ず確認するようにしましょう。 |
| 時間外労働時間数 | 残業時間を記載します。36協定の上限を超えていないか必ず確認するようにしましょう。 |
| 深夜労働時間数 | 22時〜翌5時までの労働時間を記載します。割増賃金計算の根拠となるため正確に記載してください。 |
| 休日労働時間数 | 法定休日労働時間を記載してください。代休・振替休日と混同しないよう、注意が必要です。 |
| 基本給・各種手当 | 職務手当、資格手当なども、社内規程に基づき区分して記載してください。 |
| 控除項目 | 社保、税金、社内控除を記載します。控除額が適正か、本人同意があるか確認するようにしてください。 |
| 賃金総額 | 支給合計額を記載してください。各手当・控除と一致しているか必ず確認するようにしてください。 |
| 差引支給額 | 実際の振込額を記載します。必ず給与振込明細と突合してください。 |
賃金台帳と給与明細の違い
給与明細と賃金台帳は「同じものでは?」と誤解されがちですが、両者は目的も法的性格も異なります。
主な違いについて、以下の表にまとめました。
| 項目 | 賃金台帳 | 給与明細 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 労働基準法第108条・施行規則第54条 | 労働基準法第24条(賃金の支払明細の交付義務) |
| 目的 | 賃金支払状況を事業所が内部で記録・保存し、労基署の監督やトラブル対応に備える | 従業員に対し、支給額・控除額など賃金計算の内訳を明示する |
| 記載項目 | 労働日数、労働時間、時間外労働、休日労働、深夜労働、基本給、各種手当、控除、総支給額、差引支給額など | 基本給、各種手当、控除、総支給額、差引支給額(労働時間数などは記載義務なし) |
| 様式 | 法定帳簿(フォーマットは自由だが必須項目を網羅する必要あり) | 書面または電子交付であれば形式自由 |
| 保存義務 | 最後の記入日から3年間(将来的に5年へ延長検討中) | 保存義務なし(会社の内部管理目的で残すことは可能) |
| 提出先 | 労働基準監督署から求められた場合に提示 | 従業員本人へ交付 |
| 役割 | 法令遵守・労務監査対応・賃金管理 | 従業員への説明責任・透明性の確保 |
賃金台帳は「会社が保存する帳簿」であり、労基署調査や労務トラブル時の証拠資料となる重要文書です。特に労働時間や残業時間といった「労務データ」を含む点が特徴です。
一方、給与明細は「従業員に交付する明細」で、主に「支給額や控除額の通知」が目的です。必須記載項目は限られており、労働時間などは省略される場合が多いです。
つまり、給与明細をそのまま賃金台帳として代用することはできません。人事担当者は両者の違いを理解したうえで、「社内保存用の賃金台帳」と「従業員交付用の給与明細」をそれぞれ正しく管理することが必要です。
実務での注意点
賃金台帳を作成・保管するにあたり、注意しなければならないことを以下に解説していきます。
残業・休日労働の記録が正確性かどうか
労基署調査で最も厳しく見られるのは「労働時間と賃金の整合性」です。タイムカードや勤怠システムの記録と賃金台帳の残業時間が異なれば、未払い残業代の是正勧告につながります。
各種手当の根拠が明文化されているか
役職手当や住宅手当などは、就業規則・給与規程で基準を明確化しておくことが必要です。曖昧な支給基準はトラブルの火種になります。
電子化・クラウド保存の要件を満たしているか
近年は給与システムやクラウドで一元管理するケースが増えていますが、電子帳簿保存の要件を満たした保存方法になっているか必ず確認するようにしましょう。
電子帳簿保存の主な要件は、電子帳簿保存法に基づき、
- 改ざん防止措置
- タイムスタンプの付与
- 出力・検索が可能な状態
を整えておく必要があります。
保存期間と管理ルールを遵守しているか
「最後の記入日から3年間」は必須保存期間になっていますが、法改正に伴い、5年分しっかりと保存しておく必要があります。退職者データも同様に保存対象のため注意が必要です。大量のデータを扱う場合は、年度ごとのフォルダ管理や退職者専用アーカイブを作ると後々の調査対応がスムーズになるためおすすめです。
賃金台帳の活用方法

賃金台帳は単なる“法的義務”にとどまらず、経営管理や人事戦略に役立つデータベースとして活用できます。以下に具体的な活用方法について解説していきます。
人件費分析への活用
部門別・年代別の賃金台帳データを集計することで、人件費の構造を把握することができます。残業代の比率や手当の構成など、コスト削減や給与制度改定のための重要な資料となります。
同一労働同一賃金対応への活用
賃金台帳のデータを活用すれば、正社員・非正規社員間の賃金差を客観的に比較できます。裁判や労基署調査でも証拠資料となるため、透明性の高い人事制度設計を構築することができるでしょう。
賃金格差是正・ダイバーシティ推進への活用
性別・年齢・雇用形態ごとの賃金データを分析することで、企業内の格差を可視化することができます。また、女性活躍推進法や人的資本開示にも活用することができます。
従業員への説明責任への活用
昇給・賞与の説明時に、賃金台帳を基にした数値を示すことで、説得力が増すだけではなく、従業員からの信頼感を高めることができます。
Q&A:賃金台帳に関するよくある質問
ここでは、よくある質問についてQ&A形式で解説していきます。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、賃金台帳について具体的な記載内容や実務上の注意点、活用方法まで解説してきました。
まとめると、
- 賃金台帳とは:労働基準法第108条に基づき、全事業場に作成・保存が義務付けられた法定帳簿
- 記載項目:氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間、残業・休日・深夜労働時間、各種手当、控除、総支給額・差引支給額などが必須項目
- 給与明細との違い:給与明細は従業員に交付する資料、賃金台帳は会社が保存する帳簿(労働時間などの記載が必須であり代用不可)
- 実務上の注意点:残業時間の整合性、手当の根拠の明文化、電子保存の適正管理、保存ルールの徹底が重要
- 活用方法:人件費分析、同一労働同一賃金対応、賃金格差是正、従業員への説明責任など、経営戦略にも有効
賃金台帳とは、従業員の労働条件と賃金の全体像を記録する重要な帳簿です。記載漏れや不備があると行政指導につながる一方で、正しく整備すれば経営分析や人材戦略のツールとして大いに役立ちます。
賃金台帳は、単なる法定帳簿という枠を超えて、労務管理の透明性確保と人件費の最適化を実現する基盤資料となり得ます。人事担当者は「義務だから作る」のではなく、積極的にデータを活用し、労務リスクの軽減や人材戦略の推進につなげていく姿勢が求められるのです。
自社の賃金台帳を、労務コンプライアンスと経営改善の両輪で活かしていくことが、これからの人事部門に求められる役割といえるでしょう。本記事が賃金台帳についての知識を深める一助となれば幸いです。
 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。