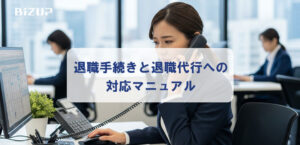人事担当者必見!面接で聞いてはいけないNG質問

「それ、普通に聞いてしまっていたかも…」
「その質問はプライバシーの侵害に当たります」
採用面接の現場では、こうした“無自覚なNG質問”が、いまだに多く存在します。
特に中小企業や現場主導で採用を進めている企業では、法令知識やガイドラインが十分に共有されていないケースも多く、面接官の感覚や経験則に頼りすぎた質問がトラブルの火種となることもあります。
本記事では、人事担当者や面接官が押さえておくべき「聞いてはいけない質問」とその背景、そして代替となる適切な質問例までを解説します。面接は、応募者と企業の信頼を築く第一歩です。信頼を損なわず、かつ有能な人材を見極めるためにも、面接におけるリスク管理を徹底しましょう。
目次
- なぜNG質問が問題になるのか
- 実はやりがち?NG質問の具体例
- 違法にならないための判断基準とは?
- 適切な質問に言い換えるには
- 社内での面接ガイドライン整備のすすめ
- まとめ:面接の質を高める第一歩は「聞かない勇気」
- 人事制度の整備に不安があるなら、人事コンサルの力を活用してみませんか?

なぜNG質問が問題になるのか

法的リスクと企業イメージの低下
面接でのNG質問が最も問題となるのは、採用差別につながる恐れがあるからです。たとえば、婚姻状況や宗教、家族構成、病歴など、業務遂行に直接関係のない個人的な質問を行うことは、厚生労働省や法務省が発行する「採用選考に関する指針」でも明確に禁止されています。
もし応募者側が不快に感じたり、不当な取り扱いを受けたと判断した場合、企業は労働局や弁護士を通じた法的措置や評判リスクにさらされる可能性があります。
「聞くつもりはなかった」では通用しない
面接現場では、「深い意味はなく、雑談のつもりだった」「場を和ませようとしただけ」といった理由で、つい不適切な質問をしてしまうケースもあります。しかし、質問された応募者側には記録も証拠も残るため、「悪気はなかった」では済まされません。
特に、SNSなどで情報が拡散しやすい現代においては、面接官個人の発言が企業全体の信頼を損なう危険もあるのです。
実はやりがち?NG質問の具体例
ここでは、企業の面接現場で実際にありがちなNG質問を項目別に紹介します。
「うちも聞いてしまっていたかも」と感じたら、今すぐ面接フローの見直しをおすすめします。
1. 家庭状況・結婚・出産に関する質問
- 「結婚の予定はありますか?」
- 「お子さんはいますか?将来的にはどうするつもりですか?」
これらは典型的なNG質問です。
特に女性に対して行われやすく、「ライフイベントにより長く働けない」という先入観が差別に直結します。
2. 宗教・思想・支持政党について
- 「宗教上の制約はありますか?」
- 「選挙ではどの政党を支持していますか?」
信教の自由・思想信条の自由を侵害する質問は、憲法上の基本的人権にも抵触します。採用とはまったく無関係な情報であるため、質問自体がNGです。
3. 本籍・国籍・民族・性別にまつわる質問
- 「どちらの出身ですか?ご両親はどこの方ですか?」
- 「外国籍の方ですか?」
これは民族差別・国籍差別につながる恐れがあります。グローバル化が進む中で、この種の質問は特に慎重に扱うべきです。
4. 病歴・障がい・通院の有無
- 「以前、病気で長期休んだことはありますか?」
- 「持病はありますか?」
これらは健康情報に関する質問であり、個人のプライバシーを侵害する可能性があります。
特に、採用を見送る材料として使用した場合は、差別的な取り扱いと見なされるリスクが極めて高いです。
5. 転職理由に対する過度な詮索
- 「前職でなぜそんなに短期間しか働いていなかったの?」
- 「以前の会社で何かトラブルがあったんですか?」
転職理由自体を聞くのは問題ありませんが、否定的なニュアンスや詮索が強い質問は要注意です。応募者が話したくない事情に踏み込んだり、過度に圧をかけるような聞き方は避けましょう。
違法にならないための判断基準とは?
厚労省・法務省・労働局のガイドラインに沿う
面接での質問内容については、以下の公的機関が明確なガイドラインを出しています。
| 機関 | 主な指針内容 |
|---|---|
| 厚生労働省 | 「公正な採用選考の基本」を示し、職業差別の回避を推奨 |
| 法務省 | 人権侵害に当たる採用差別を禁止する啓発活動を実施 |
| 都道府県労働局 | 採用におけるトラブル相談や事例報告を受付・指導 |
これらは、企業の大小にかかわらずすべての採用活動に適用されます。
「応募者本人に関係ない」「事務的に確認しただけ」などの意図でも、違反は違反です。
面接官トレーニングで無意識の違反を防ぐ
NG質問の多くは、悪意ではなく知識不足や無意識の偏見から生まれます。特に、現場リーダーやベテラン社員が面接官になる企業では、定期的なトレーニングが不可欠です。
「これは聞いていいのか?」と迷ったら、その質問が職務の遂行に本当に必要な情報かどうかを基準に判断しましょう。
適切な質問に言い換えるには

「聞いてはいけない質問が多すぎて、結局なにを聞けばいいのかわからない」
こうした悩みを抱える面接官は少なくありません。ポイントは、職務との関連性にフォーカスすることです。
職務に必要な情報を具体的に聞く
例えば以下のように言い換えることで、問題のない面接が可能です。
| NG質問 | 適切な質問例アドアド |
|---|---|
| 「お子さんはいますか?」 | 「出張や残業に関してご希望や制約はありますか?」 |
| 「病歴はありますか?」 | 「業務に支障のある健康上の配慮事項があればお知らせください」 |
| 「結婚の予定はありますか?」 | (※業務に関係ないため、質問自体を避ける) |
| 「どこ出身ですか?」 | 「勤務地について、ご希望や通勤の制約はありますか?」 |
いずれも、業務に関連した形で確認することで差別的意図を排除しつつ情報を取得できます。
言い換えのポイントと得られるメリット
言い換えは、単にリスクを避けるためだけの工夫ではありません。応募者との信頼関係を築きながら、職務に必要な情報を確実に引き出す手段でもあります。
たとえば、「お子さんはいますか?」という質問は、応募者によっては警戒感を抱く原因になりかねません。しかし、「出張や残業に関してご希望や制約はありますか?」という言い回しに変えるだけで、業務との関係性が明確になり、応募者側も安心して回答できます。
また、「病歴はありますか?」の代わりに「業務に支障のある健康上の配慮事項があれば…」とすることで、企業は必要な配慮を事前に把握できる一方、応募者にとっても公平な評価を受けられる場であると感じてもらえるようになります。
このように、適切な言い換えは
- 応募者の信頼を得る
- 本質的な情報を引き出す
- 企業の面接品質を高める
という3つの効果をもたらします。
結果として、入社後のミスマッチや離職リスクを下げるだけでなく、企業の採用ブランドそのものを強化する施策にもなります。
社内での面接ガイドライン整備のすすめ
NG質問をなくすには、企業としての仕組みづくりが重要です。
面接チェックリストと想定QAの整備
- NG質問例とその理由を明記した「やってはいけない質問リスト」
- 面接官ごとの評価項目を統一する評価フォーム
- ロールプレイを含む研修による事前共有
このようなチェック体制を整えることで、面接の質と公平性が高まります。
多様性・公平性を重視した評価フローへ
「年齢に関係なく実力を評価する」「性別や背景で判断しない」
こうしたメッセージは、制度だけでなく面接の現場で体現される必要があります。
そのためにも、全社的に評価軸を見直し、面接後のフィードバックを定期的に振り返る仕組みを構築しましょう。
まとめ:面接の質を高める第一歩は「聞かない勇気」
面接は、ただ応募者を選別する場ではありません。
「この会社は信頼できる」「安心して働ける」と思ってもらうための貴重なコミュニケーションの場です。
だからこそ、「何を聞くか」と同じくらい「何を聞かないか」も重要です。
採用トラブルを未然に防ぎ、優秀な人材の心をつかむためにも、面接設計の見直しと面接官教育に取り組むことが、企業にとっての競争力向上に繋がります。
人事制度の整備に不安があるなら、人事コンサルの力を活用してみませんか?
面接ガイドラインの整備、評価制度の設計、面接官教育…。
これらは企業にとって重要ですが、「自社だけで整備するには限界がある」と感じている人事担当者も多いのではないでしょうか。
そんな時こそ、人事制度の構築に特化した外部コンサルの力が有効です。
制度設計から社内浸透まで伴走するビズアップの人事コンサルサービスでは、無料でお見積もり・資料請求が可能です。
人を活かす制度づくりは、リスク管理の先にある戦略です。まずは無料資料で、貴社の課題に向き合ってみませんか?
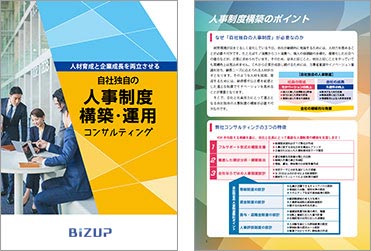 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIの
活用資料
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- e-JINZAI for service(サービス業向け)
- …その他、様々な業種に特化した資料をご覧いただけます。
資料内容
-
e-JINAIは一般企業・団体の社員教育から、各種業界向けの専門的知識まで、国内最大級の約20,000を超える動画コンテンツをご用意しています。オンライン研修プログラムの導入にご関心のある方はぜひご覧ください。