労働者名簿とは?作成義務や記載項目、実務での注意点をわかりやすく解説
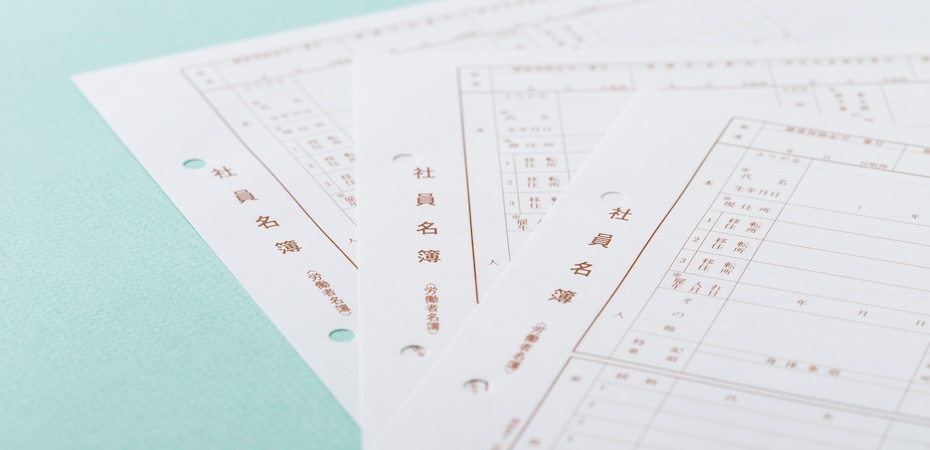
KEYWORDS 労務管理
企業が従業員を雇用する際に必ず整備しなければならない「労務管理帳簿」。その中でも労働者名簿は、労働基準法に基づいて作成・保存が義務付けられた法定帳簿のひとつです。
採用時や退職時には必ず更新が必要であり、労働基準監督署の調査時には賃金台帳や出勤簿と並んで提出を求められる重要な資料です。
しかし人事担当者の中には、
「どんな項目を記載すればいいの?」
「保存期間はどのくらい?」
「個人情報保護の観点で注意すべきことは?」
といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、労働者名簿の基本から記載項目、実務上の注意点、活用方法までをわかりやすく解説します。
目次
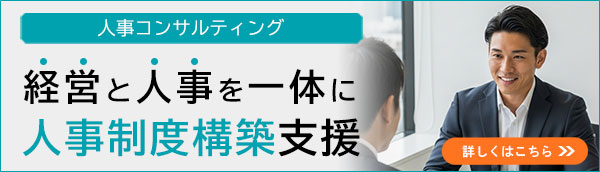
労働者名簿とは

「労働者名簿」とは、事業場において雇用するすべての労働者について、氏名や生年月日、雇入れ年月日などの基本情報を記録する帳簿です。労働基準法第107条および施行規則第53条に基づき、全ての事業場で作成・保存が義務付けられています。
主な目的は、労働者の雇用実態を把握し、労災補償や労務トラブル発生時に備えることです。労働者が退職または死亡した日から3年間保存することが義務付けられていますが、実務上は労務トラブルや労災認定請求に備えて、5年以上の保存が望ましいとされています。
労働者名簿の記載項目
労働者名簿の必須記載事項は以下のとおりです。記載内容は労働基準法施行規則第53条で厳粛に定められており、記載漏れがあると「不備」と判断され、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあるため注意が必要です。
| 項目 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 氏名 | 住民票に登録されている正式な氏名を記載してください。 |
| 生年月日 | 正確な西暦または和暦で記載してください。 |
| 性別 | 男女別に記載してください。 |
| 住所 | 現住所を正確に記載してください(緊急連絡にも活用)。 |
| 雇入年月日 | 初めて雇用契約を結んだ日付を記載してください。 |
| 退職年月日とその理由 | 退職時に必ず記録してください。解雇の場合は「普通解雇」「懲戒解雇」など具体的に記載する必要があります。 |
| 従事する業務の種類 | 職種や担当業務を記載します。部署異動があれば更新してください。 |
| 業務上の災害補償や疾病に関する事項 | 労災事故や業務上疾病が発生した場合に記録します。 |
労働者名簿と他の労務帳簿の違い
労働者名簿は、賃金台帳や出勤簿と並ぶ三大帳簿のひとつですが、それぞれ役割が異なります。それぞれの役割について以下の表にまとめました。
| 帳簿 | 主な目的 | 主な記載内容 | 実務での利用シーン |
|---|---|---|---|
| 労働者名簿 | 誰を雇用しているかを把握する | 氏名、生年月日、住所、雇入年月日、退職理由、従事業務、災害補償関連事項 | 採用・退職管理、労災対応、労基署調査 |
| 賃金台帳 | どのように賃金を支払っているかを把握する | 労働日数、労働時間、時間外・休日・深夜労働時間、基本給、手当、控除、総支給額・差引支給額 | 給与計算、残業代の確認、是正勧告対応 |
| 出勤簿(勤怠記録) | 実際の労働時間を把握する | 出勤日数、始業・終業時刻、休憩時間、遅刻・早退・欠勤、有休 | 勤怠管理、賃金計算の基礎資料、労基署調査 |
ポイント
- 労働者名簿は「誰を雇っているか」を示す名簿
→ 人事台帳としての役割が強く、雇用関係の証明に直結します。 - 賃金台帳は「賃金の内容」を示す帳簿
→ 未払い残業や賃金不払いトラブル時において重視されます。 - 出勤簿は「労働時間の実績」を示す帳簿
→ 時間外労働や休日労働の裏付け資料となります。
これら3つは相互に補完し合う関係にあり、1つでも不備があると整合性が取れなくなり、労基署から是正勧告を受けるリスクが高まります。
実務での注意点
労働者名簿を作成・保管するにあたり、注意しなければならないことを以下に解説していきます。
退職理由を記載しているか
退職理由が解雇の場合、「懲戒解雇」「普通解雇」など、具体的に記載する必要があります。自己都合退職の場合は「一身上の都合」と記載することが可能ですが、本人から提出された退職届と内容を一致させておくことが重要です。これらを曖昧にすると、労務トラブル時に「不当解雇」だと訴えられることもあるので注意が必要です。
異動や配置転換があった場合、即時更新しているか
部署変更、職務変更、役職昇格などがあれば、労働者名簿に必ず追記・更新します。更新が遅れると「実際の業務内容と記録が一致していない」と判断され、労基署調査や労災認定時に不利となってしまいます。
個人情報保護へ配慮しているか
労働者名簿には「住所・生年月日」などのセンシティブ情報が含まれています。
そのため、
- 施錠可能なキャビネットへ補完する
- 電子データの場合はアクセス権限を限定する
- 不要になった場合はシュレッダー処理やデータ消去する
などの対応が必要です。
個人情報保護法の観点からも、管理責任を明確化することも大切です。
他帳簿と整合性が取れているか
賃金台帳や出勤簿と突き合わせて矛盾がないか定期的に確認する必要があります。例えば、労働者名簿に「退職済み」と記録してあるのに、賃金台帳で給与支給が続いている、などの不一致があると、「記録の不備」とされる可能性があります。
保存期間や保存方法を工夫しているか
法令上は「退職または死亡から3年」保存義務がありますが、近年の労働紛争や未払賃金請求は5年が時効とされているため、実務では5年以上の保存が推奨されます。
保存方法の工夫として、
- 年度ごとにファイルを分けてアーカイブする
- 電子化してクラウド保存し、検索性を高める
- 退職者用フォルダを分けて管理する
などしておくと良いでしょう。
常に労基署調査に備える
定期監督や申告監督の際、労働者名簿の提出を求められることがあります。記載漏れや不備があると是正勧告の対象になるため、常に最新の情報に更新し、提出できる状態にしておくことが重要です。
労働者名簿の活用方法

労働者名簿は「誰を雇用しているか」を記録する法定帳簿ですが、きちんと整備すれば人事管理・リスク管理・人材戦略の幅広い場面で活用できます。以下に具体的な活用方法について解説していきます。
人員構成・人材データ分析への活用
労働者名簿には、氏名・生年月日・性別・雇入年月日・職種などの基本データが揃っています。これを整理・分析することで、以下のような視点で人員構成を把握できます。
- 年齢構成(若手~ベテランの比率、定年退職予定者の把握)
- 性別や雇用形態ごとの比率(男女比・正規/非正規比率)
- 勤続年数別の分布(早期離職率や長期勤続者の傾向把握)
この情報は、採用計画や後継者育成計画を立てる際の基礎資料となります。
人事異動・配置転換の参考資料として活用
労働者名簿には「従事する業務」や「部署異動の履歴」を追記していくことで、従業員ごとのキャリア履歴を管理できます。
- 過去の部署経験
- 業務スキルの蓄積
- 異動・配置転換の頻度
これをもとに「どの従業員をどの部署に配置すれば最適か」を判断することができ、適材適所の人材配置に役立ちます。
災害時・緊急時の安否確認への活用
労働者名簿には住所が記載されているため、自然災害や事故が発生した場合の安否確認リストとして利用できます。特に、勤務先が地震・豪雨などの災害リスク地域にある場合には、従業員の所在地を一覧で確認できる労働者名簿が非常に重要になります。
緊急連絡網の基盤資料としても活用でき、防災マニュアルとの連動を図ることが望ましいです。
労務トラブル・労災対応の証拠資料として活用
退職理由や業務上の災害補償に関する記録は、労務トラブルが発生した際の証拠資料となります。
例えば、
- 「懲戒解雇」と明確に記録しておくことで、後日の労使紛争時に正当性を説明できる
- 労災申請時に、従事していた業務内容を証明できる
このようなケースにおいて、正確な記録は裁判や監督署調査での対策資料として活用することができます。
人材育成・キャリア形成への活用
従業員の業務履歴や異動履歴を記録しておくことで、キャリアパス設計や教育計画の基礎データとして活用できます。
- どの業務をどれくらい経験してきたか
- 将来的に管理職候補となる人材は誰か
- スキルや経験に偏りがないか
労働者名簿を「単なる記録」から「人材育成の台帳」として活用することで、人材の成長支援や後継者育成計画につながります。
人的資本経営・法令対応への活用
近年注目される「人的資本情報の開示」や「女性活躍推進法」「高年齢者雇用安定法」などの対応にも、労働者名簿のデータが役立ちます。
- 男女比や年齢構成 → ダイバーシティ経営の指標
- 勤続年数や離職状況 → 従業員エンゲージメント分析
- 雇用形態別の割合 → 同一労働同一賃金への対応資料
名簿を正しく整備しておくことで、社外への説明責任(IR資料・CSR報告)にも活用できます。
Q&A:労働者名簿に関するよくある質問
ここでは、よくある質問についてQ&A形式で解説していきます。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、労働者名簿について、具体的な記載内容や実務上の注意点、活用方法まで解説してきました。
まとめると、
- 労働者名簿とは:労基法第107条および施行規則第53条に基づき作成・保存が義務付けられた帳簿
- 記載項目:氏名、生年月日、性別、住所、雇入年月日、退職年月日・理由、従事する業務、災害補償関連事項
- 保存期間:退職または死亡の日から3年間(実務上は5年以上推奨)
- 他帳簿との違い:賃金台帳・出勤簿と併せて整備することで、労務管理体制を強化
- 実務注意点:退職理由の具体的記載、異動時の更新、個人情報保護、整合性チェックが必須
- 活用方法:人員構成の把握、災害時対応、人材育成など経営戦略にも役立つ
労働者名簿は「義務だから作る」ものではなく、企業の人事基盤を支える重要なデータベースです。正しく整備し、経営や人材戦略に積極的に活用することで、コンプライアンスの維持と企業価値の向上の両立を実現することができるでしょう。
本記事が労働者名簿についての知識を深める一助となれば幸いです。
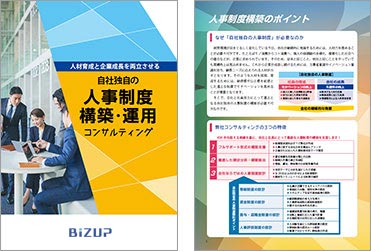 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。



