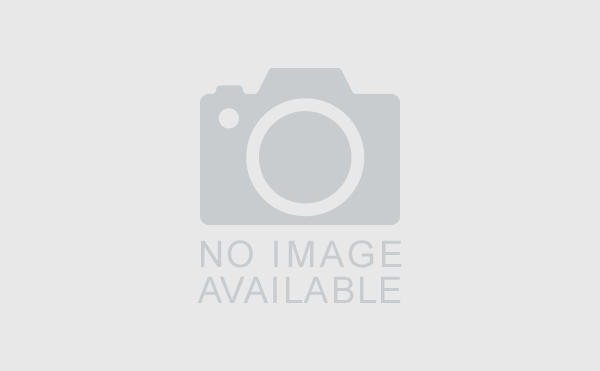労働時間規制の緩和で働き方はどう変わる?高市政権のねらいや社会的影響を解説

KEYWORDS 労務管理
2025年10月、高市首相が労働大臣に労働時間規制の緩和を指示したことが報道され、大きな話題となっています。
日本では「働き方改革」や「過労死」など、労働環境についての問題が大きな課題として度々取り上げられており、その中で今回「労働時間規制の緩和」という報道がされたことで、大きな議論を巻き起こしています。
本記事では、今回の労働時間規制の緩和報道の概要や、現在の労働環境を取り巻く問題、そして規制緩和による影響や懸念点などについてわかりやすくしていきます。
目次
高市政権における労働時間規制の緩和の概要

今回大きく取り上げられた労働時間規制の緩和に関するニュースは、具体的にはどのようなものだったのでしょうか。以下に開設していきます。
2025年10月、高市首相が労働時間規制の緩和を検討するよう労働大臣に指示しました。具体的な内容は「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行う。働き方改革を推進するとともに、安心して働くことができる環境を整備する」というものです。(参考:高市早苗首相、労働時間規制の緩和検討を指示 厚生労働相らに | 日本経済新聞 – 掲載日:2025年10月21日)
現在の日本の労働基準法では、残業時間の上限が原則として月45時間、年360時間と定められています。また、繁忙期などの特別な事情がある場合でも、月100時間未満、複数月平均で80時間以内に制限されています。これらの規制は、過労や過労死を防止するために設けられたものですが、企業の柔軟な働き方を制約する要因ともなっています。
そこで高市首相は、労働市場の変化や企業の競争力強化を背景に、労働時間規制の見直しを進める意向を示したのです。具体的には、例えば残業時間の上限を引き上げたり、フレックスタイム制を一層推進したりする方針が示されています。人手不足が叫ばれる昨今、限られた労働資源を最大限に生かすためには、柔軟な勤務時間が必要だということです。
今後は、高市政権の下で労働時間規制の緩和に向けた具体的な検討が進められるとされています。その結果、企業の働き方改革と労働者の生活の質の向上が両立するような制度の構築が期待されています。
一方で、高市首相就任時の「ワークライフバランスという言葉を捨てる」、「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」という発言や今回の指示を受け、国民の生活と健康を軽視する政策だと非難する声も挙がっています。
現在の労働時間規制とその背景
「労働基準法に基づく労働時間の規制」は、日本の労働史の中で最も重要な制度の一つであり、戦後復興期から高度経済成長期、そして平成の働き方改革へと、社会情勢に応じて何度も改正・見直しが行われてきたものです。
以下に、その成立と改正の経緯、背景を解説していきます。
1. 労働時間規制の原点
- 制定時期:1947年4月7日(日本国憲法施行の直前)
- 制定法:労働基準法(昭和22年法律第49号)
- 当時の規制内容:1日8時間、1週48時間が上限
- 休日は毎週1日以上(週休制)
第二次世界大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の指導のもとで行われた民主化政策の一環として制定されました。それまでの日本は「産業報国」的な長時間労働が常態化しており、過労死や労働災害が多発していました。新憲法(第27条)に「勤労の権利・義務」とともに「労働条件の基準は、法律でこれを定める」と明記されたことにより、初めて労働者の健康と人権を守るための包括的な法律が制定されたのです。
2. 戦後〜高度経済成長期:長時間労働の黙認時代(1950〜1970年代)
- 背景:戦後復興と高度経済成長による人手不足・生産拡大の圧力がかかる
- 実際には「8時間労働制」が形骸化し、多くの企業で残業や休日出勤が常態化
- 経済成長の裏で、労働災害・過労死・過労自殺の問題が顕在化し始める。
「法律上の上限」と「現実の働き方」に乖離が生じた時代でした。
3. 1987年改正:「週40時間制」への移行(段階的導入)
- 改正時期:1987年(昭和62年)労働基準法改正
- 改正内容:労働時間を「週48時間」から「週40時間」へ短縮(段階的に実施)
- 1997年(平成9年)に完全実施
経済成長が成熟段階に入り、「ゆとりと豊かさを重視する社会」へと価値観が転換していった時代です。
労働組合や国際労働機関(ILO)からも「過重労働是正」が強く求められていました。さらに、女性の社会進出や余暇の拡大、育児・介護との両立が政策課題となり、「働きすぎ社会」からの脱却が国策として進められたのです。
4. 1998年以降:変形労働時間制・裁量労働制の導入
- 改正法:労働基準法改正(1998年以降複数回)
- 主な内容:1か月単位・1年単位の変形労働時間制の導入
- フレックスタイム制の拡充
- 専門業務型・企画業務型裁量労働制の新設
バブル崩壊後の経済停滞と雇用構造の変化により、「成果主義」や「多様な働き方」への転換の必要性が叫ばれるようになりました。企業の国際競争力を高めるため、労働時間を柔軟に運用できる仕組みが求められました。
5. 2019年:「働き方改革関連法」による上限規制の明文化
- 施行:2019年4月1日(中小企業は2020年4月〜)
- 新しいルール:時間外労働の上限を法定化
- 原則:月45時間・年360時間
- 特例(36協定特別条項):複数月平均80時間以内・月100時間未満
- 年5日の年次有給休暇の取得義務化
電通社員の過労自殺事件(2015年)を契機に、「過労死防止法」(2014年施行)とともに、社会的に「長時間労働の是正」が最重要課題となりました。安倍政権下で「一億総活躍社会」を掲げ、健康的で持続可能な働き方を制度として確立する方向に進む中で規制が明文化されました。
そして、働き方改革関連法の規制明文化から5年が経った現在、その見直しの必要性について議論されているのです。
現在の労働時間規制の問題点

現在法律で定められている労働時間規制や、労働環境を取り巻く問題について以下に解説していきます。
長時間労働の常態化
一部の業界や企業では、労働時間が常に長時間化しており、これが過労や健康問題を引き起こしています。日本では過労死という言葉が存在するように、過度な労働時間が社会問題として顕在化しています。
過労死の労災認定基準(通称「過労死ライン」)は、以下のように定められています。
- 発症前1か月間におおむね100時間以上の時間外労働(月100時間超)
- 発症前2~6か月間にわたって1か月平均80時間以上の時間外労働(月平均80時間超)
これらの基準を超える時間外労働がある場合、業務と発症との関連性が強いとされ、労災認定の対象となります。特に運輸業や建設業など現場職では、労働時間が慢性的に長く、法定上限を超えるケースも珍しくありません。
また、厚生労働省が公表した「令和6年度 過労死等の労災補償状況」によると、過労死の請求件数は以下のようになっています。
- 運輸業、郵便業:213件
- 卸売業、小売業:150件
- 建設業:128件
特に「道路貨物運送業」においては、請求件数が155件と最多となっており、長時間労働が常態化していることが伺えます。
また、職種別では「輸送・機械運転従事者」が177件と最も多く、続いて「専門的・技術的職業従事者」が149件、「サービス職業従事者」が136件となっています。(参考:令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省/しごとより、いのち。│厚生労働省)
フレキシブルな働き方の難しさ
規制が厳しいことで、企業が柔軟な働き方を導入しにくくなっていることも問題視されています。特にリモートワークやフレックスタイム制度の導入が進んでいる昨今、規制が従業員の働き方の自由度を制限しているという指摘もあります。
人手不足と生産性の向上
少子高齢化が進み、労働力の供給が難しくなる中で、企業は労働時間の規制を緩和し、より効率的に労働力を活用したいと考えるようになってきています。特に製造業や物流業などでは、フレキシブルな勤務体系の導入が求められる場面が増えています。
労働時間規制の緩和の影響と懸念
今後の労働時間規制の緩和により、企業の経営や労働環境はどのような影響を受けるのでしょうか。また、懸念される問題などについて以下に解説していきます。
企業への影響
労働時間規制の緩和は、企業にとってさまざまな利点があると考えられています。特に、時間外労働の柔軟化やフレックスタイム制の導入は、企業の生産性を向上させる大きな要因となります。企業が規制に縛られることなく、自社に最適な労働時間を設計することができれば、業務効率化やコスト削減を行うことができます。
例えば製造業では、フレックスタイム制度を導入することで、生産ラインの稼働時間を最大化し、効率よく業務を進めることが可能になります。また、IT業界においても、リモートワークを柔軟に取り入れた労働時間管理が進んでおり、これによって社員の働きやすさと企業の生産性が向上することが期待されます。
労働者への影響と懸念
一方で、労働時間規制の緩和がもたらす懸念も多くあります。特に、過度な長時間労働が助長される恐れがあります。過労による健康被害は、社会的にも大きな問題となっており、企業が自由に働き方を設計できるようになったとしても、従業員の健康を守るためには適切なガイドラインと監視体制が必要不可欠です。
さらに、労働時間規制の緩和が進むことによって、労働者間の不平等が生まれるリスクもあります。特に非正規労働者やフリーランスの労働者は、安定した勤務時間や給与の保証がなくなることで、不安定な労働環境に陥る可能性があります。このような場合、規制緩和が企業の利益にはつながっても、労働者にとっては不利な状況を生む可能性が高くなります。
労働時間規制の緩和は、日本の企業にとって柔軟な働き方を導入するチャンスであり、従業員にとっても生活の質を高める可能性を秘めています。しかし、その一方で、過労や健康問題、さらには雇用の不平等が生じるリスクも伴います。規制緩和を進める際には、企業と労働者のバランスを保つことが最も重要です。
企業の生産性向上と従業員のワークライフバランス改善が同時に実現されるためには、過労を防止するための対策がしっかりと整備されることが大前提となります。社会全体でこの問題に取り組み、適切な働き方改革を進めていくことが大切なのです。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、今回の労働時間規制の緩和報道の概要や、現在の労働環境を取り巻く問題、そして規制緩和による影響や懸念点についてなどを解説してきました。
まとめると、
- 高市首相が労働時間規制の緩和を指示し、労働時間規制の緩和が検討されることとなった
- 現行の労働時間規制では1日8時間、週40時間が基本であるが、人手不足問題の深刻化、柔軟な働き方に則さない実態といった問題点がある
- 労働時間規制の緩和により、生産性向上と柔軟な働き方の実現両方を推進したい意向
- 規制緩和により健康問題・過労死リスクの上昇が懸念される
- 長時間労働の常態化などを防ぐため、適切に運用されるよう監視強化が必要不可欠
以上が本記事の要点となります。
労働時間規制の緩和は、生産性向上と柔軟な働き方を両立させるための政策です。しかし、法改正を悪用して長時間労働を強いるようなことは決して許されません。単に制度を緩めるのではなく、社会全体がその運用を監視し、正しく機能させることが大切です。もしこの改革が健全に実現すれば、より多くの人が自分らしく働ける社会が訪れるでしょう。
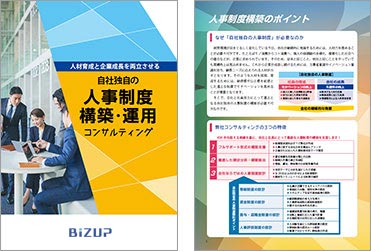 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。