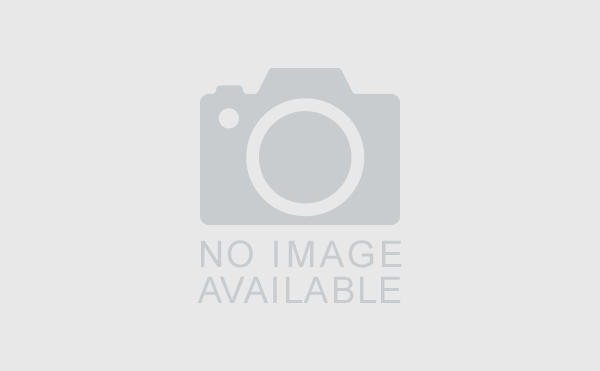【人事担当者必見】退職手続きと退職代行への対応マニュアル|法的リスクを回避する実務ガイド
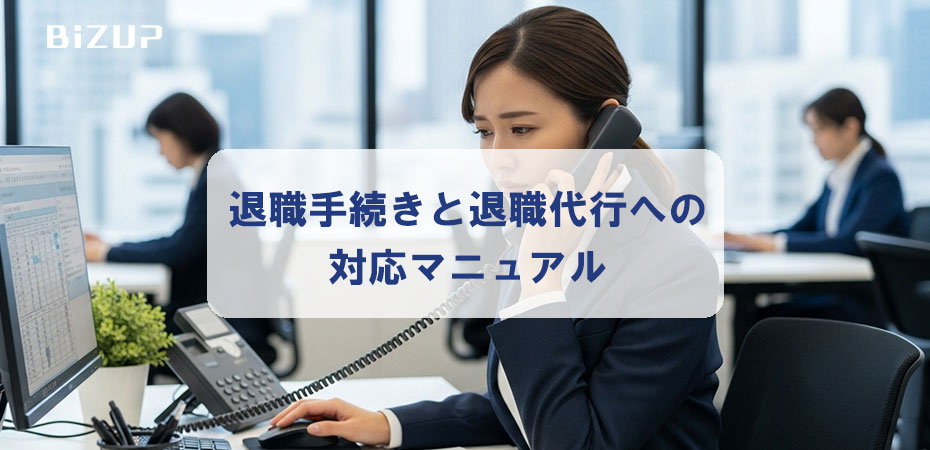
KEYWORDS 人事
人事担当者にとって、従業員の退職手続きは日常業務の一つですが、近年は退職代行サービスからの突然の連絡に戸惑うケースが増加しています。適切な対応を怠ると、労働トラブルや法的リスクに発展する可能性があります。
この記事では、人事担当者が押さえておくべき退職手続きの実務フローから、退職代行業者への適切な対応方法、トラブル予防策まで、実践的な内容を網羅的に解説します。法律に基づいた正確な知識と、現場で即活用できる具体的なノウハウをお届けします。
従業員の円満退職をサポートしつつ、企業のリスクを最小限に抑えるための実務ガイドとして、ぜひご活用ください。
目次
- 人事担当者が知っておくべき退職の基礎知識
- 退職代行サービスからの連絡への初期対応
- 退職代行業者への具体的な対応手順
- 非弁行為への対応と法的リスク管理
- 退職代行を使われた際の引き継ぎ対応
- 退職トラブルの予防と企業のリスク管理
- 退職後に発生しうるトラブルと対処法
- 円満退職を促進するための人事施策
- まとめ
人事担当者が知っておくべき退職の基礎知識
人事担当者は、退職に関する法的知識を正確に理解しておく必要があります。民法第627条により、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は退職希望日の2週間前に申し出ることで退職できます。これは法律上の最低ラインであり、労働者の権利として保障されています。
ただし、多くの企業では就業規則で1〜3ヶ月前の申し出を規定しています。この就業規則の規定は、業務の引き継ぎや後任者の確保のために設けられていますが、法的拘束力は民法よりも弱いため、従業員が2週間前の申し出を主張した場合、原則として拒否できません。
退職届と退職願の違いも重要です。退職願は「退職させてください」という相談・申し出であり、会社が承認するまでは撤回可能です。一方、退職届は「退職します」という一方的な意思表示であり、原則として撤回できません。人事担当者は、従業員から提出された書類がどちらなのかを確認する必要があります。
また、退職の自由は憲法で保障された権利です。会社は従業員の退職を拒否することはできません。「人手不足だから退職は認めない」「プロジェクトが終わるまで待て」といった対応は違法となる可能性があります。
従業員が退職を申し出た際、引き止めることは可能ですが、強制や脅迫は違法です。「退職するなら損害賠償請求する」「退職金を支払わない」などの脅しは、パワハラや脅迫罪に該当する可能性があります。
就業規則と民法の関係
就業規則で「退職は3ヶ月前に申し出ること」と定めていても、民法の2週間前の規定が優先されるケースがあります。特に、従業員が精神的に追い込まれている場合や、ハラスメントが原因の退職の場合、無理に就業規則を押し付けることは企業にとってリスクとなります。
実務上は、可能な限り就業規則に沿った退職をお願いしつつ、従業員の事情も考慮した柔軟な対応が求められます。業務の引き継ぎ期間として1ヶ月程度の猶予をもらえるよう交渉し、どうしても難しい場合は2週間での退職も受け入れる姿勢が重要です。法的紛争に発展するよりも、円満に処理する方が企業にとってメリットが大きいでしょう。
退職を拒否できるケース・できないケース
基本的に、会社は従業員の退職を拒否できません。ただし、例外的に退職のタイミングを調整できるケースがあります。
退職を調整できる可能性があるのは、有期雇用契約の期間中(やむを得ない事由がない場合)、機密情報を扱う役職で適切な引き継ぎが必要な場合、競業避止義務がある場合などです。しかし、これらの場合でも完全に拒否することはできず、あくまで退職時期の調整や条件の交渉が可能という程度です。
一方、絶対に拒否できないのは、従業員が精神疾患や体調不良を理由に退職する場合、ハラスメントが原因の退職の場合、民法に基づいて2週間前に正式に申し出た場合です。これらのケースで退職を拒否すると、企業が法的責任を問われる可能性が高くなります。
標準的な退職手続きの実務フロー
人事担当者が円滑に退職手続きを進めるためには、明確なフローを確立しておくことが重要です。
Step1:退職の申し出受理(初日)
従業員から退職の相談や退職願・退職届の提出があった際、まず提出日と希望退職日を記録します。直属の上司が受け取った場合は、速やかに人事部門に報告させる体制を整えておきましょう。この段階で、就業規則の退職に関する規定を確認し、退職理由を丁寧にヒアリングします。
Step2:退職日の調整と承認(3日〜1週間以内)
経営層や関係部署と退職日を調整し、正式に承認します。可能であれば、業務の引き継ぎ期間を確保できる退職日を提案しますが、従業員の事情も考慮した柔軟な対応が必要です。承認後は、正式な退職承認通知を文書で交付します。
Step3:退職に関する説明と書類準備(承認後すぐ)
退職者に対して、退職までのスケジュール、返却物、受け取る書類、有給休暇の残日数、退職金の有無と金額、健康保険や年金の手続きなどを説明します。チェックリストを用意しておくと漏れがありません。
Step4:業務の引き継ぎ(退職日まで)
]後任者への引き継ぎをサポートします。引継書の作成を依頼し、必要に応じて引き継ぎ状況を確認します。後任者が決まっていない場合でも、業務マニュアルやデータの整理を依頼しましょう。
Step5:貸与品の返却と書類の交付(退職日前後)
退職日までに、社員証、名刺、PC、携帯電話、制服、鍵、社用車など会社の貸与品をすべて返却してもらいます。同時に、離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書などを交付します。
Step6:退職後のフォロー(退職後)
離職票の発行(退職日から10日以内)、最終給与と退職金の支払い、住民税の手続きなどを確実に行います。また、退職者から問い合わせがあった場合に備えて、連絡窓口を明確にしておきましょう。
【表1:退職手続きの標準スケジュールとチェックリスト】
| タイミング | 人事担当者の対応 | 必要書類・確認事項 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 退職申し出当日 | 申し出受理、日付記録、理由ヒアリング | 退職願 / 退職届受領 | 上司からの報告体制確認 |
| 3日〜1週間 | 退職日調整、経営層承認、通知交付 | 退職承認通知書 | 従業員の事情も考慮 |
| 承認後すぐ | 退職手続き説明、スケジュール共有 | 退職手続きチェックリスト、有給残日数確認 | 書面で記録を残す |
| 退職日まで | 引き継ぎ状況確認、最終給与計算 | 引継書、業務マニュアル | 引き継ぎの進捗管理 |
| 退職日 | 貸与品回収、必要書類交付 | 貸与品リスト、返却確認書 | 漏れがないよう現物確認 |
| 退職後10日以内 | 離職票発行、雇用保険手続き | 離職票、雇用保険資格喪失届 | 期限厳守(法定義務) |
| 退職月末 | 最終給与・退職金支払い | 源泉徴収票 | 未払い賃金がないよう確認 |
退職代行サービスからの連絡への初期対応
退職代行サービスからの連絡は、多くの場合、朝の始業時間前に電話やメール、LINEなどで突然届きます。人事担当者としては冷静に、かつ慎重に対応する必要があります。
初期対応の基本原則
まず、退職代行業者からの連絡を受けた際は、慌てずに相手の情報を確認します。業者名、担当者名、連絡先、従業員の氏名、所属部署などを記録しましょう。この時点で、いきなり退職を承諾したり拒否したりせず、「確認します」という姿勢を保つことが重要です。
次に、退職代行業者の種類を確認します。一般企業が運営しているのか、労働組合なのか、弁護士なのかによって、対応方法が変わります。弁護士や労働組合からの連絡の場合、法的な交渉権限があるため、より慎重な対応が必要です。
確認すべき重要事項
従業員本人の意思確認が最優先です。退職代行業者を通じてでも、本人が確実に退職を希望しているのか、本人の署名入りの退職届があるのかを確認します。ただし、本人への直接連絡は、退職代行業者から「本人への連絡は控えてください」と要請されている場合、慎重に判断する必要があります。
退職希望日と理由も確認します。即日退職を希望しているのか、2週間後なのか、それとも就業規則に沿った期間での退職なのかを明確にします。また、退職理由によっては、会社側の対応を見直す必要があるケースもあります。
記録の重要性
退職代行業者とのやり取りは、すべて記録に残しましょう。電話の場合は通話内容をメモし、可能であれば録音します(相手に録音の同意を得ることが望ましい)。メールやLINEの場合は、すべて保存します。後々のトラブル防止に、これらの記録が重要な証拠となります。
社内への報告
退職代行からの連絡を受けたら、速やかに経営層、総務・法務部門、該当従業員の直属の上司に報告します。独断で判断せず、関係部署と連携して対応方針を決定することが重要です。特に、法的リスクが予想される場合は、顧問弁護士への相談も検討しましょう。
【表2:退職代行業者の種類別対応マトリックス】
| 業者種類 | 法的権限 | 対応レベル | 交渉可否 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 一般企業 | なし(伝達のみ) | 通常 | 不可 | 非弁行為に注意、交渉要求は拒否可能 |
| 労働組合 | あり(団体交渉権) | 慎重 | 可能 | 交渉拒否は不当労働行為のリスク |
| 弁護士 | あり(全般) | 最慎重 | 可能 | 法的措置の可能性、顧問弁護士と連携 |
| 不明・疑わしい | 不明 | 最慎重 | 保留 | 業者の身元確認を最優先 |
退職代行業者への具体的な対応手順
退職代行業者への対応は、段階的かつ慎重に進める必要があります。以下の手順に従って対応しましょう。
Phase 1:業者の確認と情報収集(初日)
まず、相手が本当に正規の退職代行業者なのかを確認します。業者の正式名称、所在地、連絡先、担当者の氏名を聞き取り、可能であればウェブサイトで実在を確認します。弁護士の場合は弁護士登録番号、労働組合の場合は組合名と所属を確認しましょう。
次に、従業員本人との関係を確認します。委任状や退職届のコピーの提出を求め、本人の署名や印鑑があるかを確認します。電子署名やメールでの指示の場合、本人確認がより慎重に必要です。
Phase 2:退職の意思と条件の確認(1〜2日目)
退職希望日、退職理由、有給休暇の消化希望、未払い賃金の有無、退職金の請求、貸与品の返却方法、書類の受け取り方法などを詳細に確認します。これらの情報をもとに、社内で対応方針を協議します。
この段階で、顧問弁護士に相談することも検討しましょう。特に、未払い賃金の請求や損害賠償の懸念がある場合は、法的アドバイスを受けることが重要です。
Phase 3:社内調整と対応方針の決定(2〜3日目)
経営層、直属の上司、総務・法務部門と連携し、退職を受け入れるか、条件交渉をするかを決定します。基本的には、法律に従って退職を受け入れる方向で調整しますが、引き継ぎ期間の確保や有給消化の時期など、交渉可能な点を整理します。
Phase 4:正式な回答と手続きの開始(3〜5日目)
退職代行業者に対して、会社の対応を正式に文書で回答します。退職を承認する場合は、退職日、最終出勤日、有給消化の取り扱い、貸与品の返却方法、書類の交付方法、最終給与の支払日などを明記します。
Phase 5:退職手続きの実施(退職日まで)
従業員本人が出社しない場合、郵送で必要な書類のやり取りを行います。貸与品は宅配便での返送を依頼し、受領書を交わします。業務の引き継ぎが困難な場合は、可能な範囲で資料やデータの提供を求めますが、強制はできません。
Phase 6:退職後の手続き完了(退職後)
離職票の発行、最終給与と退職金の支払い、源泉徴収票の交付などを確実に行います。すべての手続きが完了したら、退職代行業者にも完了報告を行い、今後の連絡窓口を伝えておきます。
やってはいけないNG対応
退職代行業者への対応で絶対に避けるべき行動があります。まず、退職の拒否や脅迫的な発言は厳禁です。「退職は認めない」「損害賠償請求する」などの発言は、録音されて法的証拠として使われる可能性があります。
また、本人への直接連絡の強行も避けるべきです。退職代行業者を通じて「本人への連絡は控えてください」と要請されているにもかかわらず、執拗に本人に連絡することは、ハラスメントと見なされる可能性があります。
退職金や最終給与の支払い拒否も違法です。「突然辞めたから退職金は払わない」という対応は、労働基準法違反となります。感情的な対応は避け、法律に従った処理を心がけましょう。
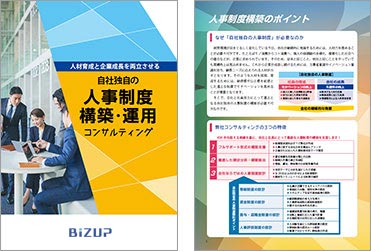 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。
非弁行為への対応と法的リスク管理
退職代行サービスの中には、弁護士資格を持たないにもかかわらず、法律事務(交渉など)を行う業者が存在します。これは弁護士法第72条に違反する「非弁行為」にあたります。人事担当者は、この点を理解し、適切に対応する必要があります。
非弁行為とは
弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で法律事務を業として行うことを非弁行為といいます。具体的には、一般企業が運営する退職代行サービスが、有給休暇の消化交渉、未払い賃金の請求、退職日の交渉などを行うことは非弁行為に該当する可能性があります。
一般企業の退職代行サービスができるのは、本人の退職の意思を伝えることのみです。それ以外の交渉行為を行おうとする場合、会社側は「弁護士資格をお持ちですか」「労働組合ですか」と確認し、資格がない場合は交渉を拒否できます。
労働組合の団体交渉権
ただし、労働組合が運営する退職代行サービスの場合、憲法第28条と労働組合法に基づく団体交渉権があるため、会社との交渉が可能です。労働組合からの団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒否すると、不当労働行為として法的責任を問われる可能性があります。
したがって、退職代行業者が労働組合であることを主張する場合、その確認を行った上で、誠実に交渉に応じる必要があります。労働組合の場合は、組合名称、所在地、代表者名、組合員番号などを確認しましょう。
会社側の対応戦略
非弁行為を行う業者に対しては、「貴社は弁護士法人または労働組合ですか」と確認し、一般企業である場合は「交渉権限がないため、退職の意思の伝達のみ承ります」と回答します。ただし、退職自体を拒否することはできないため、退職は受け入れつつ、不当な要求には応じない姿勢を示します。
もし業者が非弁行為を継続する場合、弁護士会や警察に相談することも可能ですが、実務上は、本人の退職自体は受け入れ、不当な要求のみを拒否する対応が現実的です。
【表3:業者種別による対応可否の判断基準】
| 要求内容 | 一般企業 | 労働組合 | 弁護士 | 会社の対応 |
|---|---|---|---|---|
| 退職意思の伝達 | ◯ | ◯ | ◯ | 受理する |
| 退職日の交渉 | × | ◯ | ◯ | 資格確認後に対応 |
| 有給消化の交渉 | × | ◯ | ◯ | 資格確認後に対応 |
| 未払い賃金の請求 | × | ◯ | ◯ | 資格確認後に対応 |
| 退職金の交渉 | × | ◯ | ◯ | 資格確認後に対応 |
| ハラスメント等の損害賠償 | × | △ | ◯ | 弁護士対応が原則 |
退職代行を使われた際の引き継ぎ対応
退職代行を利用される場合、従業員が出社しなくなるケースが多く、通常の引き継ぎが困難になります。人事担当者は、業務への影響を最小限に抑える対策を講じる必要があります。
即日退職の場合の対応
従業員が即日退職(その日から出社しない)を希望する場合、まず業務の緊急度を確認します。顧客対応中の案件、進行中のプロジェクト、締め切りが迫っている業務などをリストアップし、優先順位をつけます。
次に、退職代行業者を通じて、最低限必要な引き継ぎ情報の提供を依頼します。業務マニュアル、顧客リスト、進行中の案件の状況、データの保存場所、パスワードなどの情報を、メールやオンラインストレージで共有してもらうよう交渉します。ただし、強制はできないため、協力を「お願い」するスタンスが重要です。
代替要員の確保
退職者の業務を誰が引き継ぐかを迅速に決定します。同じ部署の他のメンバー、他部署からの応援、派遣社員の手配、新規採用などの選択肢を検討し、最も現実的な方法を選択します。特に専門性の高い業務の場合、外部の専門家への委託も検討しましょう。
顧客やクライアントへの説明
退職者が顧客対応を担当していた場合、速やかに後任者を紹介し、引き継ぎを行います。「担当者が退職代行を使って辞めた」などの詳細は伝えず、「担当者変更により」といった表現で説明するのが適切です。顧客への影響を最小限に抑えることが最優先です。
データとアクセス権限の管理
退職者のメールアカウント、社内システムへのアクセス権限、クラウドサービスのアカウントなどを速やかに停止します。ただし、メールアカウントは、顧客からの問い合わせが来る可能性があるため、自動返信を設定した上で一定期間保持することも検討します。
退職トラブルの予防と企業のリスク管理
退職代行を使われること自体が、企業にとっては職場環境の問題を示すシグナルである可能性があります。人事担当者は、退職トラブルを予防し、企業のリスクを管理する視点を持つことが重要です。
退職代行を使われる原因の分析
従業員が退職代行を利用する主な理由は、パワハラやセクハラ、過重労働、退職の引き止め、上司に直接言いにくい雰囲気などです。自社で退職代行が使われた場合、その原因を冷静に分析し、職場環境の改善につなげることが重要です。
特に、同じ部署や同じ上司の下で複数の従業員が退職代行を利用している場合、その部署や上司に問題がある可能性が高いです。人事担当者は、退職理由を丁寧に聞き取り(退職代行業者経由でも可能な範囲で)、組織的な問題を発見する努力が必要です。
就業規則と退職ルールの見直し
就業規則の退職に関する規定が現実的かどうかを見直しましょう。「退職は6ヶ月前に申し出ること」など、過度に厳しい規定は、退職代行の利用を促進する要因となります。業界標準に合わせた、現実的な期間設定が望ましいでしょう。
また、退職手続きのフローを明確化し、従業員に周知することも重要です。「退職を申し出たらどうなるのか」が明確であれば、従業員も安心して退職を伝えることができます。
退職面談の実施と改善
従業員が退職を申し出た際、人事担当者または第三者が退職面談を実施することで、本音を聞き出し、職場改善につなげることができます。直属の上司だけで退職対応を完結させると、パワハラなどの問題が隠蔽される可能性があります。
退職面談では、退職理由、職場環境の問題点、改善してほしいことなどを率直に聞き取ります。この情報は、組織の改善や離職率の低下に役立ちます。
相談窓口の整備
従業員が退職を考える前に相談できる窓口を整備しましょう。社内相談窓口、外部の相談サービス、産業医、カウンセラーなど、複数の相談ルートを用意することで、問題の早期発見と解決が可能になります。
ハラスメント対策の強化
パワハラやセクハラは、退職代行の利用を促進する最大の要因です。ハラスメント防止研修の実施、ハラスメント相談窓口の設置、迅速な調査と対応体制の構築など、ハラスメント対策を強化することが、退職代行の利用を減らすことにつながります。
退職者データの分析
退職者の属性(年齢、勤続年数、部署、退職理由など)を定期的に分析し、傾向を把握しましょう。特定の部署や年齢層で退職率が高い場合、そこに問題がある可能性があります。データに基づいた改善策を実施することで、離職率の低下につながります。
退職後に発生しうるトラブルと対処法
退職手続きが完了した後も、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。人事担当者は、これらのトラブルに適切に対処する準備をしておく必要があります。
未払い賃金の請求
退職後に「残業代が未払いだった」「休日出勤の手当が支払われていない」といった請求を受けることがあります。労働基準法では、賃金請求権の時効は3年(2020年4月以降に発生した賃金)です。
対策としては、退職時に最終給与の明細を詳細に説明し、未払いがないことを確認してもらうことが重要です。もし請求を受けた場合は、タイムカードや勤怠記録を確認し、事実関係を調査します。未払いが確認された場合は、速やかに支払う必要があります。
ハラスメント等の損害賠償請求
退職後に、在職中のパワハラやセクハラを理由に損害賠償請求を受けるケースがあります。退職代行を利用した従業員の中には、職場環境に問題があったケースも多く、後日、弁護士を通じて請求してくることがあります。
このようなケースでは、速やかに顧問弁護士に相談し、事実関係の調査を行います。ハラスメントの事実が確認された場合、示談交渉や和解を検討する必要があります。また、加害者とされる上司や同僚へのヒアリングも慎重に行います。
機密情報や顧客情報の持ち出し
退職者が機密情報や顧客情報を持ち出し、競合他社に転職したり、独立して使用したりするケースがあります。特に、退職代行を利用して突然辞めたケースでは、貸与品の返却確認が不十分になりがちです。
予防策としては、退職時に秘密保持誓約書や競業避止誓約書に再度署名してもらうことが有効です。もし情報漏洩が発覚した場合は、直ちに弁護士に相談し、法的措置を検討します。
離職票や源泉徴収票の発行遅延トラブル
離職票の発行が遅れると、退職者が失業保険を受給できず、トラブルになることがあります。離職票は退職日から10日以内に発行することが法律で義務付けられています。源泉徴収票も、退職後1ヶ月以内の発行が義務です。
退職代行を利用された場合でも、これらの書類の発行義務は変わりません。担当者は、期限を厳守し、確実に書類を交付する体制を整えておく必要があります。郵送する際は、配達記録が残る方法を使用し、後日のトラブルを防ぎます。
社会保険の資格喪失手続きの漏れ
健康保険や厚生年金の資格喪失手続きを怠ると、退職者が国民健康保険や国民年金に加入できず、無保険状態になることがあります。退職日から5日以内に手続きを完了し、健康保険資格喪失証明書を交付する必要があります。
円満退職を促進するための人事施策
退職代行サービスの利用を減らし、円満退職を促進するためには、日頃からの人事施策が重要です。従業員が安心して退職を相談できる環境を整えることで、突然の退職や退職代行の利用を防ぐことができます。
オープンなコミュニケーション文化の醸成
従業員が上司や人事に対して、キャリアの悩みや退職の相談をしやすい雰囲気を作ることが重要です。定期的な1on1ミーティング、キャリア面談、従業員満足度調査などを通じて、従業員の本音を聞き出す機会を設けましょう。
特に、「退職を考えている」という相談があった際、頭ごなしに否定するのではなく、まず話を聞く姿勢が大切です。悩みを解決できれば退職を思いとどまってもらえる可能性もありますし、仮に退職する場合でも円満に進めることができます。
キャリア開発支援
社内でのキャリアパスを明確にし、成長機会を提供することで、「この会社にいても成長できない」という理由での退職を防げます。研修制度、資格取得支援、社内公募制度、ジョブローテーションなどを整備しましょう。
労働環境の継続的改善
過重労働、ハラスメント、不公平な評価などの問題を放置すると、従業員は退職代行を使ってでも辞めたいと考えるようになります。労働時間の適正管理、ハラスメント防止、公正な評価制度などを継続的に改善することが、離職率の低下につながります。
退職者の声を活かす
退職面談で得られた情報や、退職者アンケートの結果を真摯に受け止め、組織改善に活かすことが重要です。同じ理由で複数の従業員が退職している場合、それは明確な改善ポイントです。
退職者との良好な関係維持(アルムナイ施策)
円満退職した従業員とは、退職後も良好な関係を維持することが、企業のブランディングにもつながります。アルムナイネットワーク(退職者ネットワーク)を構築し、再雇用の道を開いておくことで、優秀な人材が戻ってくる可能性もあります。

まとめ
人事担当者にとって、退職手続きと退職代行への対応は、法的知識と実務スキルの両方が求められる重要な業務です。従業員には退職の自由があり、会社は基本的にこれを拒否できないことを理解した上で、適切な対応を行う必要があります。
退職代行サービスからの連絡を受けた際は、慌てず冷静に、業者の種類を確認し、法的権限の有無を見極めることが重要です。非弁行為には毅然と対応しつつ、労働組合や弁護士からの正当な要求には誠実に応じる姿勢が求められます。
しかし最も重要なのは、退職代行を使われないような職場環境を日頃から整備することです。オープンなコミュニケーション、ハラスメント防止、適切な労働時間管理など、基本的な人事施策の徹底が、円満退職を促進し、企業のリスクを最小化します。
本記事の内容を参考に、法令遵守と従業員の権利尊重を両立させた、適切な退職対応を実現してください。