給与制度の「号俸」「俸給表」とは?基本から役割まで解説

KEYWORDS 給与制度
給与制度の整備は、企業経営および人事制度において避けて通れない重要なテーマです。なかでも「俸給表(賃金表)」は、社員の給与額を体系的に規定し、制度の公平性と透明性を支える要となる仕組みです。とはいえ、古い設計のまま使われていたり、設計から運用に至るまで複雑化してしまい、かえって運用が困難になっている企業も少なくありません。特に中小企業では、人事・賃金制度に割けるリソースや専門知識が限られており、改善が進みづらいのが現実です。
そこで本記事では、まず「俸給表」と「号俸」という言葉の意味と仕組みを整理し、一般企業でどのように活用できるかを含めて解説します。さらに、制度が果たす役割、構成要素、よくある課題、そして設計・運用をスムーズに進めるための実践的なアプローチへと踏み込みます。給与制度を“しくみ”として捉え直し、自社に合った給与体系の構築につなげるためのヒントをお届けします。
目次
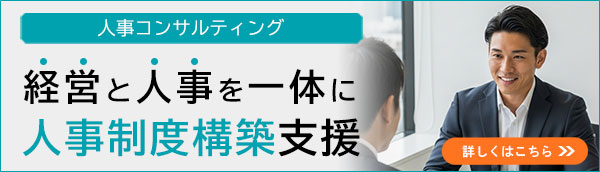
俸給表とは何か
「俸給表」とは、社員の等級(職能・役割等による分類)や号俸(給与段階)に応じて基本給等の金額を一覧化したものです。給与の決定基準を可視化し、あいまいな評価や不明瞭な昇給・昇格ルートを排除しやすくするのが大きな特徴です。例えば「2級5号」や「3級10号」といった具合に、等級と号俸の組み合わせで給与テーブル上の位置を定めることで、社員が「自分はどこにいるのか」「次にどこへ進めば給与が上がるのか」を理解しやすくなります。
一般企業では、「俸給表」という名称だけでなく「賃金表」「号俸表」などの呼び方をされることもあります。これらは基本的には同じ構成(等級 × 号俸)をベースにしていますが、「号俸」という語を使うことで、公務員的な給与制度の仕組みを参考にした設計であることを暗示している場合もあります。
俸給表は単なる給与計算の補助ツールではなく、人材の定着やモチベーションの向上に直結する制度基盤です。そのため、企業が将来の成長を考えるうえで、重要な役割を担っているといえるでしょう。
号俸とは何か
「号俸(ごうほう)」とは、給与制度において、等級内の給与段階を示す番号(号)を付し、その号に応じて基本給額を決定する枠組みです。
一般的には、等級(職務レベル・役割レベル)を横軸、号俸を縦軸、もしくは号俸を縦軸に、賃金額を交差点においた俸給表(号俸表)を作成します。号俸は通常、勤続年数・年齢・職務遂行能力・評価結果などによって上昇します。
例えば、同じ「2級」の等級に属する社員がいたとして、経験年数やスキルが異なれば号俸が「10号/12号」と分かれ、給与額も変わるという設計です。号俸が上がれば「昇給」、等級が上がれば「昇格(昇級)」というように、社員のキャリアステップが細かく設計されます。
民間企業でも、号俸の概念を取り入れて「等級×号俸」構造を持つ賃金表を設けるケースが増えており、制度設計上、より細かく給与を可変化させたい企業には有効な手法です。
制度における俸給表の役割
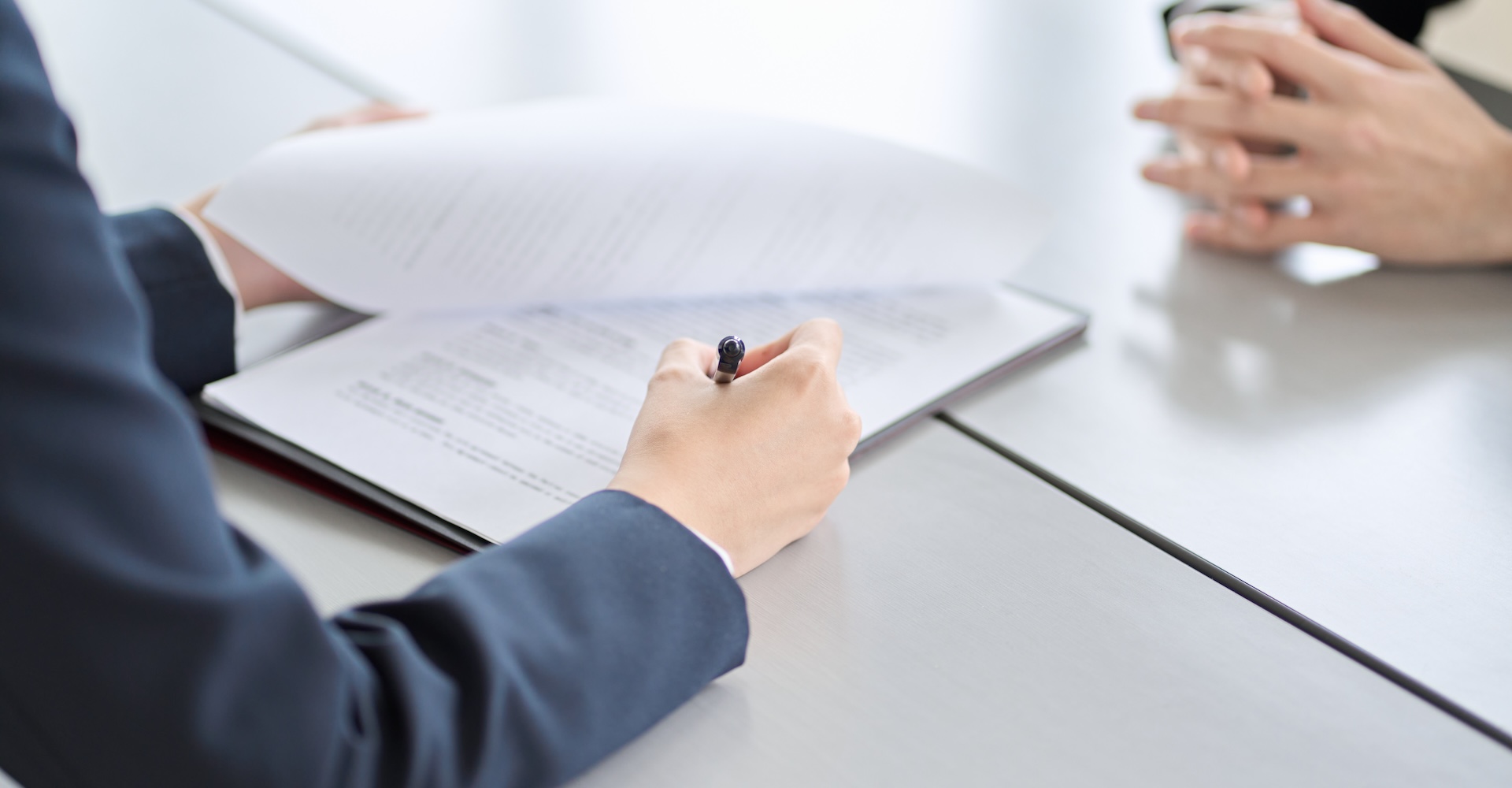
給与制度の中で俸給表が果たす役割は大きく、主に三点に整理できます。第一に、公平性の確保です。給与の決定基準を明文化することで、不透明さを排し、社員の納得を得られるでしょう。第二に、透明性の向上です。社員自身が「自分がどの位置にいるか」「次にどう昇給できるのか」を理解しやすくなるのです。第三に、将来の人件費計画に資する点です。制度が数字として整理されているため、長期的なコストシミュレーションが行いやすくなります。
このように、俸給表は単なる給与の目安にとどまらず、経営戦略と人材マネジメントを結びつける基盤としての役割を持っています。特に中小企業にとっては、優秀な人材の確保や社員定着のために不可欠な仕組みといえるでしょう。
俸給表の基本構成
俸給表の構成要素はおおよそ以下のとおりです。
- 等級(グレード): 職務・役割のレベルを示す
- 号俸: 等級内での給与段階(号数)
- 基本給(または俸給): 等級+号俸により定められた金額
以下に簡単な例を示します。
| 等級 | 号俸 | 基本給額 |
|---|---|---|
| 等級1 | 1号 | 200,000円 |
| 等級1 | 2号 | 205,000円 |
| 等級2 | 1号 | 230,000円 |
| 等級2 | 2号 | 235,000円 |
| 等級3 | 1号 | 260,000円 |
| 等級3 | 2号 | 265,000円 |
このような表を導入することで、昇給・昇格のルートが視覚化され、運用しやすくなります。とはいえ、実務上は職種別賃金表を分けたり、専門職や技術職に別枠を設けたりと、柔軟な設計が求められるケースも多々あります。
よくある課題と失敗例
俸給表は給与制度を体系化する有効な仕組みですが、実際の運用では複数の課題が生じやすい特徴があります。複雑化による理解不足、市場水準との乖離、評価制度との不整合などは特に多くの企業で見られる問題でしょう。さらに、他社制度を安易に流用してしまい、自社に適合しない制度を抱えてしまうケースも少なくありません。ここでは代表的な課題を三つに整理して解説します。
制度の複雑化による混乱
俸給表の等級や号俸を細分化しすぎると、社員にとって分かりにくい制度となりがちです。たとえば、等級が多すぎると自分がどの段階にいるのか把握できず、昇給の道筋も不透明に感じやすくなります。その結果、制度への信頼を失い「不公平ではないか」という疑念を持たれる恐れがあります。制度は詳細に設計するほど精緻に見えますが、運用が複雑化すればかえって納得感を損ねてしまうのです。制度の簡潔さと理解しやすさを確保することが重要でしょう。
市場水準との乖離とその影響
俸給表を長期間改定しない場合、業界や地域の給与水準から大きく離れてしまいます。市場の平均よりも低い給与レンジで運用していると、優秀な社員の流出が加速するだけでなく、新規採用にも悪影響を及ぼすでしょう。特に中小企業では、大手企業との差が強調されやすく、採用競争力を失いかねません。また、市場水準に合わせた更新を怠ると、社員の「待遇が業界標準より劣っている」という不満が募ります。制度を維持するためには、定期的な外部データの収集と反映が欠かせないのです。
評価制度との不整合
俸給表は本来、人事評価と連動して初めて機能する仕組みです。しかし、現実には「評価されても給与に反映されない」という不満が多く聞かれます。評価制度と俸給表がかみ合わないと、社員は成果を上げても報われないと感じ、制度への信頼を失ってしまうでしょう。特に中小企業では、評価結果をどう給与に結び付けるかの設計が不十分な場合が目立ちます。公平性を確保するためには、評価基準と昇給ルールを明確に関連付け、社員が納得できる仕組みを整えることが不可欠です。
課題解決のためのアプローチ

俸給表・号俸制度の課題を解決に導くには、段階的な進め方が現実的です。最初のステップは現状把握であり、自社の給与データや離職率、業界水準を調査して課題を明確にすることから始めます。そのうえで「制度の目的は何か」を再定義することが欠かせません。俸給表を単なる給与算出の道具とするのではなく、人材育成やキャリア形成を支援する仕組みと捉えることで、方向性が定まります。
次に、評価制度との連動を強化する必要があります。その際のポイントは以下の通りです。
- 成果や能力を正しく反映させること
- 経営層と現場の声をすり合わせること
- 社員代表を交えて協議し、納得度を高めること
こうした工夫によって、社員の意欲向上と制度の定着を同時に実現できます。
さらに、制度に定期的な見直しを組み込むことも有効です。具体的には、労働市場の変化や法改正に柔軟に対応できるようにすることです。制度をそのまま放置すると陳腐化する恐れがあるため、継続的な調整が欠かせません。
最後に、一社だけでこれらの取り組みを完結させるのは負担が大きいため、専門家の知見を活用する選択が現実的です。外部の視点を導入することで、自社の課題に即した解決策を効率的に取り入れられるでしょう。
社内で進める際の注意点
制度改定を社内だけで進めると、どうしても主観的・内部の都合に偏りがちです。担当者の経験だけに頼ると偏った設計になり、社員の納得感を欠く結果になりえます。また、社員への説明不足や変更時の周知が不十分だと、突然の号俸改定や等級変更に対して反発が出る可能性があります。そのため、「なぜ変えるのか」「どう変えるのか」「自分はどうなるのか」を丁寧に社内に説明することが制度定着の鍵です。情報共有と対話こそが、公平性・透明性を担保するうえで不可欠です。
データ分析を活用した制度改善
俸給表改定を成功させるには、感覚ではなくデータを根拠とすることが重要です。業界平均賃金、地域別賃金、同規模企業の給与水準、離職率や募集応募数などのデータを収集・分析することで、説得力ある設計が可能になります。また、号俸テーブルを定期的に更新し、時代や企業環境に応じてチューニングを行うことで、制度の陳腐化を防ぐことができます。データを用いることで、社員説明も説得力が増し、納得感のある制度運用につながります。
外部リソースとの併用
制度改定を社内だけで完結させようとすると、どうしても視野が狭くなりがちです。業界団体の調査資料やコンサルタントによる事例紹介を参考にすれば、より実効性の高い制度を作ることができます。外部のリソースをうまく取り入れることで、時間やコストの節約にもつながり、改定作業の精度も向上するでしょう。
人事コンサルの活用メリット
俸給表・号俸制度を効果的に見直すには、やはり人事コンサルタントの活用が有効です。まず第一に、外部視点による客観的な診断が受けられます。自社のみでは気づきにくい課題も、コンサルタントの分析によって明らかになります。第二に、豊富な事例に基づく提案が可能です。多数企業の成功・失敗のパターンを知るコンサルタントからの設計支援は、制度設計の近道になります。
さらに、将来を見据えた制度設計が可能となります。人件費予測・成長ステージ・等級構築などを含め、中長期的な視点で設計支援を受けられる点も大きな強みです。また、経営層・現場・人事担当と役割ごとに意見調整を進める場面でも、外部の提案を根拠とすることで合意形成がスムーズになる傾向があります。
 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。
まとめ
俸給表は、給与制度の中核を担う仕組みであり、給与決定の基準を可視化し、公平性・透明性を担保するために欠かせません。号俸という言葉を用いた等級×号俸という構造を理解し、一般企業にも応用することで、給与制度をより戦略的・納得性の高いものにすることが可能です。一方で、設計・運用を誤ると、制度の複雑化・市場水準との乖離・評価制度との不整合という課題を招き、制度疲弊の原因にもなりえます。制度を単なる給与決定のツールとしてではなく、人材育成・キャリア設計・経営戦略と連動させることで、社員の定着・モチベーション向上・企業成長を一体的に実現できます。
もし現在、自社の給与制度に「等級・号俸・俸給表の設計が曖昧だ」「昇給ルートが見えない」「運用管理が負担になっている」といった課題を感じているなら、ぜひ外部の知見を取り入れてみてください。ビズアップの人事コンサルサービスでは、無料見積もり相談を通じて自社に最適な設計の方向性をご提案いたします。公平で納得感のある給与制度を整備し、社員の定着と企業の成長につなげていきましょう。



