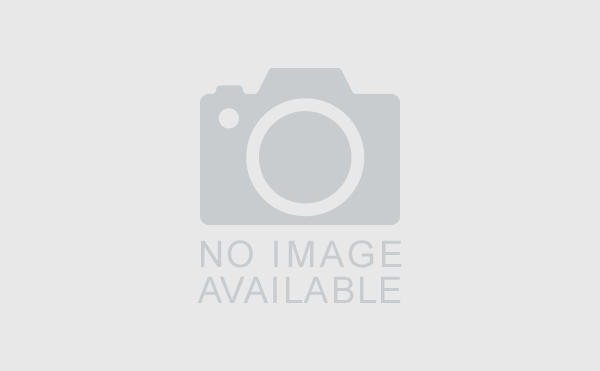【例文付き】異動願いの書き方は?能力不足を理由にするのはあり?徹底解説

組織で働く中で、「今の部署の働き方が自分に合わない」「どうしても異動したい」と感じる場面があるかもしれません。その際に提出する書面がいわゆる「異動願い」です。提出自体は一つの希望表明ですが、書き方次第では“自分勝手”な印象を与え、かえってマイナス評価につながるリスクもあります。
特に「能力不足」を理由に異動を求める場合、ネガティブな自己評価がそのまま伝わると、本人の成長意欲や組織への貢献意欲が疑われる恐れがあります。そこで本記事では、異動願いを出す前に押さえておきたい書き方の基本と「能力不足」を理由にする可否・表現の工夫、さらに具体的な例文を交えてご紹介します。しっかり準備して、希望が通りやすい申請につなげましょう。
目次
- 異動願いを出す前に押さえるべきポイント
- 「能力不足」を理由にするのはあり?
- 異動願いの書き方ステップと構成
- 例文付き:実際に使えるテンプレート
- 異動願い提出後のフォローと注意点
- まとめ:異動願いは「会社と自分、両方に貢献する提案」に
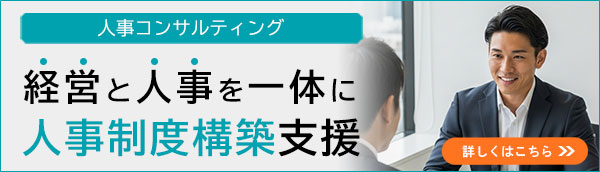
異動願いを出す前に押さえるべきポイント

異動願いは、自分のキャリアを前向きに切り拓く手段のひとつです。しかし、単に「今の仕事が合わない」「気持ちが乗らない」といった感情だけで提出すると、かえって逆効果になることも。まずは下準備として、会社の制度やタイミング、人間関係などを冷静に整理しておくことが大切です。以下のポイントを踏まえて準備を進めましょう。
会社の制度や就業規則を確認する
異動には社内公募制度や人事ローテーションの方針など、会社ごとに独自のルールがあります。制度に即した形で希望を出すことで、手続きがスムーズになり、現実的な検討対象として扱ってもらいやすくなります。申請可能な時期や異動の頻度、書式なども事前に確認しておきましょう。
直属の上司・人事との信頼関係を築く
異動願いは書面だけで判断されるものではなく、普段の業務姿勢や社内でのコミュニケーションも大きな判断材料になります。上司との関係ができていれば、希望理由を真摯に受け止めてもらえる可能性が高まります。「応援したいと思える人材かどうか」は、評価に大きく影響します。日常の言動や姿勢が土台になると心得ましょう。
部署の繁忙期や人事異動時期との兼ね合いを考える
人員が不足しているタイミングや年度末などの繁忙期に異動願いを出すと、内容に関係なく却下されるリスクがあります。逆に、人事異動の準備期間など、検討余地が生まれるタイミングを狙えば、受け入れられる可能性が高まります。異動希望は「いつ言うか」も重要な戦略の一部です。とで「希望だけ」ではなく「建設的な提案」として上司・人事に受け取ってもらいやすくなります。
「能力不足」を理由にするのはあり?
結論からいえば、「能力不足」を異動理由として挙げること自体は問題ではありません。ただし、そのままストレートに表現してしまうと、ネガティブに受け取られやすく、社内評価や将来の配置に影響を与えるリスクもあります。
書き方の工夫とリスク回避
「能力不足だから異動したい」という趣旨は、一見すると正直な自己申告ですが、このままではマイナス印象につながる可能性があります。なぜなら、会社側には「この社員は今の部署で力を発揮できていない」という評価に繋がるからです。
ただし、書き方や理由の見せ方を工夫すれば、ネガティブな印象を最小限に抑え、前向きな異動願として伝えることは可能です。以下のようなポイントを活用しましょう。
- 自己否定だけで終わらせず、「別の環境でより力を発揮できる」といった前向きな方向性を示す。
- 弱みを理由にせず、むしろ「強みがより活きる部署で貢献したい」という観点に置き換える。
- 現部署で学んだことや成果を示しつつ、異動先での具体的な貢献意欲を述べる。
- 提出時には「現在までの貢献に感謝しつつ」「会社の成長に貢献したい」という姿勢を明示する。
こうした工夫を加えることで、「能力不足」というキーワード自体を使わず、むしろ「新しい環境で挑戦したい」というポジティブな動機に変換できます。会社・上司にとって「この社員を応援したい」と思われる文脈を構築することが重要です。
異動願いの書き方ステップと構成
書面構成の基本:件名・宛名・本文・署名
異動願いの書面には基本的な構成があり、以下項目を抑えることでフォーマットとして整います。
- 提出日・宛名(例:経営企画部 部長 ◯◯ 殿)
- タイトル(「異動願」)
- 所属・社員番号・氏名・押印
- 希望部署・時期・理由
- 結び(以上/よろしくお願い申し上げます)
本文において、まず「希望異動先」と「希望時期」を明記し、次に「希望理由」と「異動後の貢献意欲」を述べる流れが標準的です。箇条書きで整理しても読みやすくなります。
書く際のポイント
- 本文はA4用紙1枚程度、簡潔にまとめる。
- ネガティブな文言(「苦手」「できません」など)は避け、前向きな表現に置き換える。
- 希望部署で自分がどう活かせるか、具体的に言及する。
- 現部署での感謝や学びにも触れることで印象が柔らかくなる。
この構成を守ることで、上司・人事が理解しやすい形式で希望を伝えられます。
例文付き:実際に使えるテンプレート
例1:スキル活用を目的とした異動希望
このパターンは、現在の部署で成果を上げた実績を踏まえて、それを次の部署でどう応用したいかを明確に伝える構成です。「スキルの横展開」や「実績の再活用」を軸に書くと、前向きな成長意欲として受け取られやすくなります。
2025年11月1日
営業部 部長 様
異動願
営業部 社員番号12345 田中 太郎
このたび、○○部署(希望部署)への異動を希望いたします。
-
現在の所属部署(在籍年数):営業部(在籍3年)
-
異動希望先:営業企画部
-
異動希望時期:2026年1月1日
-
異動希望理由:営業経験を活かして、顧客分析や営業戦略立案に貢献したいため
現在、3年間営業部に所属し、顧客ニーズのヒアリングを通じて提案力を磨き、昨年度は契約件数を前年比120%にて達成いたしました。
この経験を活かして○○部署にて、顧客データ分析および営業支援の実務に取り組み、御社の売上拡大と部門強化に貢献したいと考えております。なお、異動希望時期は2026年1月1日付を希望いたします。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
以上
例2:能力不足を「強み転換」して書く
この例では、現部署で「成果を出しにくい理由」を否定的に書かず、「別の業務で強みを活かしたい」と前向きに転換している点がポイントです。能力不足を遠回しに表現しつつ、ポテンシャルへの期待を感じさせる構成になっています。
2025年11月1日
人事部 部長 様
異動願
技術部 社員番号67890 鈴木 次郎
- 現在の所属部署(在籍年数):技術部(在籍2年)
- 異動希望先:営業支援部
- 異動希望時期:2026年4月1日
- 異動希望理由:技術部にて設計業務に従事してまいりましたが、設計工程よりも顧客折衝・要件定義のフェーズに強みを感じております。これにより設計部門内での担当範囲が限定されてしまい、もっと幅広く貢献したいという思いが強くなりました。
そこで、営業支援部への異動を希望いたします。私の技術的な知見を活かしながら、顧客視点に立った提案業務に参画し、チーム全体の提案力向上に寄与できると確信しております。
異動希望時期は2026年4月1日付を希望いたします。
以上、何卒ご検討いただけますようお願い申し上げます。
例3:部署環境・働き方を理由にした異動
この文面は、業務への興味やモチベーションの変化を背景に、異動後のキャリアビジョンを丁寧に描いています。現部署での経験と異動先の業務がつながっているため、説得力があり、社内での成長を期待させる申請となっています。
2025年11月1日
総務部 部長 様
異動願
総務部 社員番号13579 山本 花子
-
現在の所属部署(在籍年数):総務部(在籍4年)
-
異動希望先:人事部 人材開発課
-
異動希望時期:2026年4月1日
-
異動希望理由:入社以来、総務部勤続4年目となりました。最近は在宅勤務の普及に伴い、勤務形態と連動した人事制度企画に興味を持つようになり、より制度・組織に関わる仕事を通じてキャリアアップを図りたいと考えております。
つきましては、人事部 人材開発課への異動を希望いたします。総務部で培った社内制度理解・社員対応の経験を活かし、社員満足度向上・制度運営改善のために貢献したく存じます。異動希望時期は2026年4月1日付とさせていただきます。
以上、よろしくお願い申し上げます。
異動願い提出後のフォローと注意点

異動願いを提出すればそれで終わり、というわけではありません。提出後の対応や社内での振る舞い次第で、今後のキャリア形成や評価に影響を及ぼすこともあります。冷静な姿勢と誠実な対応を心がけることで、異動の実現だけでなく、信頼の積み重ねにもつながります。
進捗確認と相談
異動願いを出したあと、しばらく返答がないと不安になるのは当然です。とはいえ、すぐに催促するのは避けたいところ。提出後1~2週間程度のタイミングで、業務報告の流れの中で自然に「その後の検討状況はいかがでしょうか」とさりげなく尋ねるのが効果的です。聞き方にも配慮し、あくまで“相談”というスタンスを崩さないことが大切です。
現在の部署での態度を維持する
異動願いを出した後、「もうこの部署を離れるから」と気を抜いてしまうのは絶対に避けたい行動です。たとえ異動が内々に決まっていても、最後まで前向きに仕事へ取り組む姿勢が評価されます。異動願いはあくまで「次に進むための希望」であり、今の部署での実績が次のステージを左右することを忘れてはいけません。
異動が叶わないときの対応
すぐに希望が通らなかった場合でも、がっかりして終わるのではなく、今後のキャリア形成のヒントを得る機会ととらえましょう。「なぜ通らなかったのか」「どのような経験が必要なのか」を上司と話し合うことで、次に向けた準備が明確になります。また、異動に限らず配置転換やプロジェクト参加など、視野を広げて別の成長機会を模索することも、前進するための選択肢です。
まとめ:異動願いは「会社と自分、両方に貢献する提案」に
異動願いを書く際には、ただ「自分が変えたいから異動したい」ではなく、「自分がこう変わることで、会社や部署にどう貢献できるか」を明確に伝えることが鍵です。特に「能力不足」というテーマを扱う場合には、ネガティブな要素をそのまま書くのではなく、自分の強みを活かして新しい環境で価値を提供したいという構成にすれば、上司・人事にも前向きに受け止められやすい言い回しになります。
書き方・構成・理由の伝え方を丁寧に設計し、提出後も現在の部署で誠実に働き続けることで、異動への道筋をつくりましょう。適切なタイミング・形式・書き方を意識して、自分と組織の双方にとって有益な異動願いを目指してください。
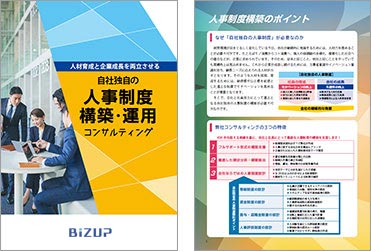 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。