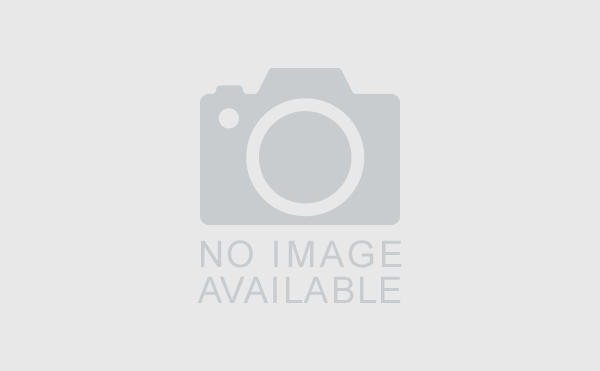キャリアコンサルタントとは?資格の概要・試験内容・取得メリットをわかりやすく解説

人生100年時代といわれる現在において、働き方や生き方が多様化する中で「自分らしいキャリア」を見つめ直す人が増えています。そんなキャリア形成支援の専門家として注目を集めている「キャリアコンサルタント」。企業における人材育成や転職支援、学生のキャリア教育など、幅広い分野で活躍できる国家資格として注目度が高まっています。
本記事では、キャリアコンサルタントとはどのような資格なのか、その役割や試験概要、取得のメリット、そして実際にどのような活躍の場があるのかを詳しく解説します。
(参考:キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント|厚生労働省)
目次
- キャリアコンサルタントとは
- キャリアコンサルティング技能士との関係性
- キャリアコンサルタント資格試験の概要
- 注意すべきポイント
- 学習計画の立て方
- キャリアコンサルタント資格取得のメリット
- 将来性と今後の需要
- まとめ
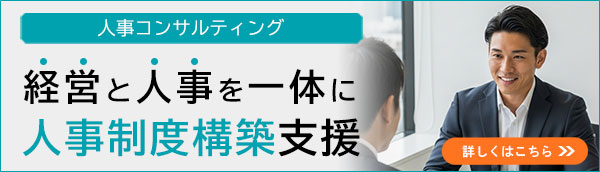
キャリアコンサルタントとは
キャリアコンサルタントとは、働く人一人ひとりの職業選択やキャリア形成を支援する専門家です。
「職業能力開発促進法 第30条の3」に基づく国家資格であり、この資格を持たない者は、業務として「キャリアコンサルタント」を名乗ることはできません(名称独占資格)。
キャリアコンサルタントは、以下のような場面で活躍します。
- 就職・転職を希望する人へのキャリアカウンセリング
- 学生に対する進路指導やキャリア教育
- 企業内での人材育成・キャリア開発支援
- 再就職支援やリスキリング(再教育)のサポート
- メンタルケアを含むキャリア面談
単なる「就職支援」ではなく、「本人がどのように生きていきたいか」「どんなキャリアを築きたいか」を一緒に考え、支援するのがキャリアコンサルタントの使命です。
また、「職業能力開発促進法」第11条、第12条において、事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、「事業内職業能力開発計画」を作成するとともに、その実施に関する業務を行う「職業能力開発推進者」を選任するよう努めることと規定されています。
さらに、平成30年7月の職業能力開発促進法施行規則等の改正によって、職業能力開発推進者を「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するものと規定されました。このように法制度としてもキャリア支援の重要性が高まり、企業・個人双方でキャリアコンサルタントの役割が拡大しています。
キャリアコンサルティング技能士との関係性
キャリアコンサルタントと似た名称の資格で、キャリアコンサルティング技能士というものがあります。両者を比較すると、キャリアコンサルタントはキャリア支援の専門家として厚生労働省が認定する国家資格の入口資格です。一方「キャリアコンサルティング技能士」は、キャリアコンサルタントとして一定の実務経験を積んだ後に受験できる上位資格(技能検定)にあたります。技能士は「キャリアコンサルティング技能士2級」と「1級」に区分され、2級は個人支援を中心とした熟練レベル、1級は組織全体のキャリア支援や後進指導を担う上級レベルとされています。
つまり、キャリアコンサルタントが「基礎資格」であり、技能士はその専門性と実践力を証明する「実務能力資格」といえます。両者を組み合わせることで、より高度で信頼性の高いキャリア支援が可能となります。
キャリアコンサルタント資格試験の概要

キャリアコンサルタント試験は、厚生労働省が指定する以下の2機関が実施しています。
どちらの団体を選んでも「国家資格」としての効力は同じですが、試験内容の傾向や評価基準に若干の違いがあります。詳しい試験内容について、以下に解説していきます。
受験資格
キャリアコンサルタント資格試験を受けるには、次のいずれかを満たす必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | キャリアコンサルティングの実務経験3年以上 |
| 養成講座修了 | 厚生労働大臣が認定した講習(養成講座)を修了している |
| 他資格経由 | 旧制度の「キャリア・コンサルタント能力評価試験」合格者など |
※最も一般的なのは「養成講座修了」ルートです。大学や民間教育機関が実施する講座を半年~1年かけて受講し、修了証を得た後に国家試験を受験します。
試験構成
キャリアコンサルタント資格試験は以下の3つの試験で構成されています。
- 学科試験:キャリア理論・カウンセリング理論・労働法など、キャリア支援に必要な知識を幅広く問う四択式の筆記試験。全50問・100点満点で、70点以上が合格基準です。
- 実技試験(論述):相談事例を読み取り、クライエントの課題把握や支援方針を記述する筆記試験。理論理解と論理的思考力、文章による表現力が評価されます。
- 実技試験(面接):ロールプレイ形式でクライエント役との面談を行い、傾聴力・共感力・質問力・倫理観などを総合的に評価。実際の相談対応力を測る最重要試験です。
学科試験と実技試験(論述)は同日に行われ、実技試験(面接)は別日に行われます。受験料金は、学科試験が8,900円、実技試験が29,900円です(※金額は変更となる可能性があります)。
(参考:令和7年度・令和8年度の試験日程)
試験科目と内容
- 職業能力開発促進法その他関係法令に関する科目:労働基準法や雇用保険法、職業安定法など、労働者の権利保護や職業能力開発に関する法律を理解し、適正なキャリア支援を行うための法的知識を問う科目です。
- キャリアコンサルティングの理論に関する科目:ホランドやスーパー、シャインなどのキャリア理論や発達理論を学び、相談者のキャリア課題を科学的・体系的に理解する力を問う科目です。
- キャリアコンサルティングの実務に関する科目:面談技法、傾聴、質問、要約などのカウンセリングスキルを中心に、相談現場での対応力や実践的支援の方法を問う科目です。
- キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目:キャリア支援が社会・経済・企業・教育に果たす役割を理解し、多様な働き方や生涯キャリア形成を支援する社会的意義を問う科目です。
- キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目:守秘義務、公正性、専門職としての倫理判断、スーパービジョンの活用など、相談業務を行う際の倫理的態度と行動指針を問う科目です。
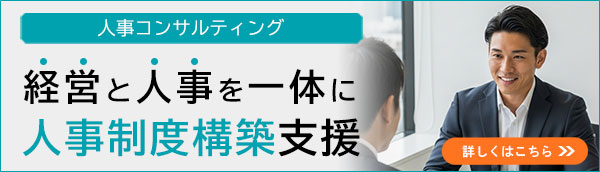
注意すべきポイント
キャリアコンサルタント資格取得にあたり、注意すべきポイントについて以下に解説していきます。
名簿登録を忘れずに
合格後は、キャリアコンサルタント名簿に登録することが必要となります。登録事務は、厚生労働大臣が指定登録機関として指定した特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会が行います。
登録更新が必要
キャリアコンサルタントの登録を継続するためには5年ごとに更新を受ける必要があります。更新を受けるためには、キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な「知識」と「技能」の維持を図るための講習を一定時間数以上受講の上、更新を行ってください。
学習計画の立て方
キャリアコンサルタント試験の学習期間は、一般的に6か月~1年程度が目安です。必要な学習時間は合計300~400時間ほどとされ、仕事や育児をしながらでも無理のない計画を立てることが合格への近道です。
- 最初の1~2か月は「基礎固め」の期間として、キャリア理論・カウンセリング理論・法制度の理解を中心に進めます。代表的な理論(ホランド・スーパー・シャインなど)を押さえつつ、労働関連法規や職業能力開発制度の概要も学びましょう。
- 3~4か月目は「実践力の養成期」として、ロールプレイや模擬面談を通じて実技対策を強化します。カウンセリング技法(傾聴・質問・要約・承認など)を体得するため、録音・フィードバックを繰り返しながらスキルを磨くことが重要です。また、論述試験対策として、事例分析・要約・記述練習にも取り組みます。
- 5か月目以降は「総仕上げ期間」として、過去問演習や模擬試験で得点力を高めます。学科・実技の両面から復習を行い、特に苦手分野を徹底的に補強します。試験直前期は、倫理・守秘義務・理論の整理など知識の再確認を重点に置きましょう。
| 期間 | 学習時間の目安 | 学習内容例 |
|---|---|---|
| 1〜2か月目(基礎固め期) | 約80〜100時間 | ・キャリア理論(ホランド・スーパー・シャインなど)の基礎理解 ・カウンセリング理論(ロジャーズ・ゲシュタルトなど)の学習・職業能力開発促進法や労働関連法規の概要を習得 |
| 3〜4か月目(実践強化期) | 約120〜150時間 | ・ロールプレイ演習による面談技法の習得(傾聴・要約・質問・承認) ・事例分析を通じた課題把握力、助言力の強化 ・論述試験対策(文章構成・要約練習・理論との関連づけ) |
| 5か月目(応用・模試期) | 約60〜80時間 | ・過去問・模擬試験で実践的な得点力を養成 ・苦手分野の再学習と理論、法令の整理 ・ロールプレイの録音、振り返りによる改善練習 |
| 6か月目(最終調整期) | 約40〜60時間 | ・試験直前対策(倫理・守秘義務・キャリア理論の総復習) ・模試での時間配分確認と記述練習 ・面接時の言語表現、姿勢、非言語コミュニケーションの最終確認 |
日々のスケジュールにおいては、平日は1~1.5時間、週末は3~4時間を確保するのが理想です。短時間でも継続的に学習を積み重ねることが、合格への最短ルートとなるでしょう。
キャリアコンサルタント資格取得のメリット

キャリアコンサルタント資格を取得することにより、たくさんのメリットを得ることができます。以下に具体的なメリットについて解説していきます。
- 国家資格としての信頼性:厚生労働省認定の国家資格であり、専門職としての社会的信用が高く、転職・昇進・社内評価の際にも高く評価されやすいです。
- 自分自身のキャリア形成に役立つ:キャリア理論や自己理解の手法を学ぶことで、自分の強み・価値観・働き方を整理でき、将来設計に活かすことができます。
- 他者支援のスキルが身につく:傾聴・質問・承認などのカウンセリングスキルが養われ、人との関係づくりやコミュニケーションにも役立ちます。
- 幅広い分野で活躍できる:企業の人事部門、教育機関、公的機関、民間の転職支援会社など、多様な業界で資格を活かすことができます。
- 人的資本経営時代に求められる人材:社員のキャリア面談や人材育成を担う専門家として、企業内での存在感が高まっています。
- 副業・独立が可能:オンラインキャリア相談、研修講師、再就職支援など、フリーランスとして活動できるチャンスがあります。
- 社会貢献につながる:働く人の生き方や再就職を支援することで、労働市場の活性化や地域貢献に寄与することができます。
- 一生使える専門資格:更新制度によりスキルを継続的に磨きながら、長期的に活躍できる生涯資格であることも強みです。
| 分野 | 主な活躍先 | 業務内容の例 |
|---|---|---|
| 企業・組織内 | 人事部・研修部・相談窓口 | 社員のキャリア面談、キャリア研修の企画運営 |
| 教育機関 | 大学・高校・専門学校 | 学生の進路相談、キャリアガイダンス実施 |
| 公的機関 | ハローワーク・ジョブカフェ | 再就職支援、職業紹介、職業訓練相談 |
| 独立・フリー | キャリア相談室、オンラインカウンセリング | 個人相談、講演、企業研修、講師活動 |
このようにキャリアコンサルタント資格は、「自己理解の深化」と「他者支援による社会的意義」を兼ね備えた、キャリアと人生を豊かにする実践的な資格といえます。
将来性と今後の需要
キャリアコンサルタントの需要は今後ますます拡大すると予測されています。背景には、急速な技術革新やAIの普及、働き方改革、人生100年時代の到来など、労働環境の多様化があります。企業では「人的資本経営」が重視され、社員一人ひとりのキャリア形成支援やリスキリング(再教育)の推進が急務となっています。これに伴い、キャリアコンサルタントが企業の「社内キャリアアドバイザー」として配置されるケースも増加中です。
また、教育分野では高校・大学でのキャリア教育が強化され、学生の進路支援や職業意識形成に携わる専門家としての役割が高まっています。加えて、定年延長や転職の一般化により、中高年層の再就職支援やセカンドキャリア相談のニーズも急増しています。
このように、キャリアコンサルタントは「働くすべての世代の人生支援者」として、今後の社会に不可欠な存在となるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、キャリアコンサルタントについて、その役割や試験概要、取得のメリットなどを解説してきました。
まとめると、
- キャリアコンサルタントは、国家資格として信頼性が高く、幅広い分野で活躍可能
- 「自己理解の深化」と「他者支援による社会的意義」を兼ね備えた実践的な資格である
- 上位資格として、キャリアコンサルティング技能士2級と1級がある
- 試験は学科と実技の2部構成で、登録や更新が必要
- 学習期間は一般的に6か月~1年程度が目安で、必要な学習時間は合計300~400時間ほど
- 今後の人的資本経営時代において、企業・教育・行政いずれの現場でも需要が拡大中
以上が本記事の要点となります。
キャリアコンサルタントは、単に「仕事の相談に乗る人」ではありません。人が自分らしく働き、生きるための道をともに考え、寄り添いながら成長を支援する専門家です。働き方や価値観が多様化する今、キャリアコンサルタントは、企業・教育・行政・地域社会のあらゆる場面で必要とされています。
誰かの人生を支えながら、自らのキャリアも豊かに育てていく——。人と社会の未来をつなぐ架け橋として、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。本記事が、キャリアコンサルタントの知識を深める一助となれば幸いです。
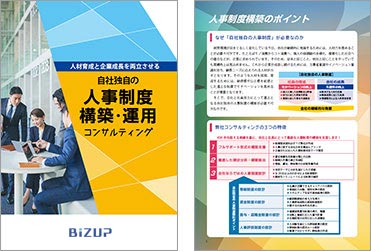 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。