定年と誕生日の関係を正しく理解しトラブルを防ぐ方法

人事担当者の方なら、「定年退職日は誕生日当日なのか、それとも前日なのか?」という質問を受けたことがあるかと思います。最近では「誕生日の前日に退職して損をした」と感じる社員の声も聞かれます。
実はこの「損」には、社会保険の資格喪失日のタイミングや、失業保険(雇用保険の基本手当)の年齢区分の違いなども関係しています。
この記事では、定年と誕生日の関係を法律・実務両面から整理し、人事担当者が押さえるべき就業規則の書き方、手続き上の注意点、社員説明のコツを詳しく解説します。
目次
定年退職日の基本を理解する
定年とは何か?法的な定義を確認しよう
定年とは、「労働者が一定の年齢に達したことを理由に労働契約を終了する制度」を指します。
高年齢者雇用安定法第8条では、企業に「60歳未満の定年禁止」を義務付けています。したがって、60歳以降であれば企業ごとに定年を定めることが可能です。
ただし、その「定年日=いつをもって労働契約終了とするか」を明確にしておかないと、給与・退職金・社会保険・雇用保険の全てに影響します。
定年日の設定方法と特徴
| 設定方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 誕生日(例:60歳の誕生日) | シンプルで理解しやすい | 年齢計算法上「前日」が到達日になるため、誤解が生じやすい |
| 誕生日月の月末 | 給与・社会保険処理が容易 | 一時的に60歳超過勤務となる |
| 賃金締切日(例:20日) | 勤怠管理・給与処理と整合 | 定年条項に具体的明記が必要 |
「誕生日退職」の意外な落とし穴
年齢計算の法律:「誕生日の前日に年齢到達」
年齢の計算については、「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)および民法第143条により、次のように定められています。
「年齢は誕生日の前日の終了時(午後12時)にその年齢に達する。」
つまり、「60歳の誕生日当日」が60歳になる日ではなく、誕生日の前日が満60歳到達日と扱われます。
たとえば、4月1日生まれの社員は、3月31日の午後12時に満60歳に達するため、「満60歳の誕生日をもって定年退職」と就業規則に定めていると、退職日は3月31日になります。
事例:「誕生日の前日に退職して誤解が生じた」Aさんの場合
Aさん(60歳)は、就業規則に「満60歳の誕生日をもって定年退職」と記載された企業で勤務していました。
本人は誕生日当日まで働くつもりでしたが、実際の退職日は3月31日(誕生日の前日)とされ、
- 誕生日当日(4月1日)は既に退職後のため出勤できなかった
- 社会保険の資格喪失日が4月1日(退職日の翌日)となった
- 本人が期待していた勤務日数と1日のズレが生じた
という結果に。
「知らずに誤解した」と感じたAさんのようなケースは、年齢計算法の理解不足によって起こります。
「失業保険」にも影響する”誕生日前日退職”
雇用保険の年齢判定も「誕生日の前日」基準
雇用保険(失業給付)の支給日数は、退職時の年齢と加入年数、離職理由によって決まります。
そして、その「年齢」は年齢計算法に基づき「誕生日の前日」で判断されます。
つまり、誕生日の前日に退職すると、法律上はすでに誕生日を迎えている=1歳上の年齢として扱われるのです。
退職時の年齢による支給日数の違い
【自己都合退職の場合】
| 退職時の年齢 | 被保険者期間 | 支給日数 |
|---|---|---|
| 全年齢共通 | 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 90日 | |
| 10年以上20年未満 | 120日 | |
| 20年以上 | 150日 |
※自己都合退職の場合、年齢による支給日数の違いはありません
【会社都合退職(特定受給資格者)の場合】
| 退職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
ポイント:
- 会社都合退職では、60歳未満(45歳以上)で最大330日
- 60歳以上になると最大240日に減少
- つまり、59歳11か月で退職するか、60歳(誕生日前日)で退職するかで、支給日数が大きく変わる可能性がある
再雇用制度と退職日のタイミング
多くの企業では、定年後も継続して働ける「再雇用制度」を導入しています。
しかし、定年退職日を誕生日の前日とすると、翌日(誕生日当日)に再雇用契約を結ばない限り、その間が”空白日”扱いになる可能性があります。
結果として、
- 社会保険・雇用保険の資格喪失・再取得の手続きが必要
- 継続雇用であるにもかかわらず、形式上「一度退職」となる
- 高年齢雇用継続給付の申請タイミングに注意が必要
という手続き上の注意点が発生します。
就業規則を見直し、誤解と手続きミスを防ぐ
定年条項の記載例
誤解を防ぐには、定年条項の文言を見直すことが最も効果的です。
例1:月末退職とする場合
満60歳に達した日の属する月の末日をもって定年退職とする。
例2:翌月末退職とする場合
満60歳の誕生日の翌月末日をもって定年退職とする。
例3:誕生日当日を明確にする場合
満60歳の誕生日の前日をもって定年退職とする。
このように明確に記載すれば、「前日退職」の誤解を防ぎつつ、給与・保険処理も円滑に行えます。
社内説明と研修でルールを共有
定年制度の理解不足は、社員だけでなく管理職・人事担当者にも見られます。そのため、以下のような社内研修・説明会を実施することが有効です。
| 研修内容 | 対象 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 定年退職日の法的基礎 | 人事・総務担当者 | 年1回 |
| 年齢計算の仕組みと事例演習 | 管理職 | 半年に1回 |
| 退職予定者向け定年制度説明会 | 定年前3年~ | 年2回 |
研修を通じて「なぜ誕生日前日が年齢到達日なのか」を正しく共有することが、誤解防止につながります。
「誕生日の前日に退職し損をした」を防ぐために
「損をした」と感じる主な理由を整理すると、以下のように分類されます。
| 損の内容 | 原因 | 主な影響 | 対策 |
|---|---|---|---|
| ① 勤務日数のズレ | 年齢到達日の誤解 | 本人が想定していた勤務日との相違 | 定年日を月末扱いに変更、または事前説明の徹底 |
| ② 社会保険・手続き上の複雑化 | 退職日と再雇用日の調整不足 | 資格喪失・取得のタイミングのズレ | 退職日・再雇用日の整合を取る |
つまり、「損」の本質は“日付のズレによる誤解と手続きの複雑化”です。
これを防ぐには、人事部門が制度・法律・就業規則を一体で運用し、事前の丁寧な説明を行う必要があります。

まとめ
「誕生日の前日に退職し損をした」というトラブルは、小さな文言の違いから生じる、大きな実務上のリスクです。
人事担当者は次の3つを実践しましょう。
- 就業規則を見直し、定年日の明確な記載を行う
- 雇用保険・社会保険の手続きを日付ベースで確認する
- 定年前説明会・社内研修を通じて社員へ制度理解を促す
これらを徹底することで、社員が安心して定年を迎えられ、企業としても信頼性を高めることができます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
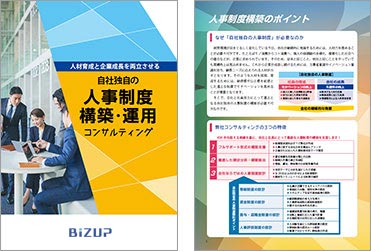 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。



