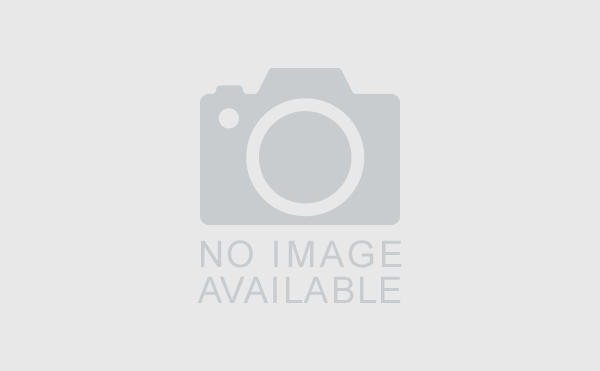人的資本経営とは?経営者が今こそ向き合うべき「人を資産とする経営」の実践ポイントを徹底解説

近年注目されている「人的資本経営」をご存じでしょうか。
少子高齢化や働き方の多様化が進む中、企業の競争力を左右するのは「人材力」です。人的資本経営は、この「人材力」に焦点を当て、人をコストではなく“資本”として捉えることで企業を成長させるという経営手法です。本記事では、その概要や重要性、実践のステップ、経営者やるべきことなどについてわかりやすく解説していきます。
目次
人的資本経営とは
「人的資本経営(Human Capital Management)」とは、従業員を単なるコストではなく「資本」として捉え、その能力・意欲・経験を最大限に発揮させることで企業価値を高めていく経営手法を指します。財務資本や設備投資だけでは競争優位を維持できない時代において、「人」が最も重要な経営資源であるという考え方です。
| 観点 | 従来の考え方 | 人的資本経営 |
|---|---|---|
| 人材の位置付け | コスト/資源(ヒト・モノ・カネの一つ) | 資本としての投資対象 |
| 投資意識 | コスト削減・効率性重視 | 投資対効果を重視、成果を可視化 |
| 意思決定基準 | 勘・経験・直感が中心 | データ・指標を用いた合理性重視 |
| 目的・視点 | 短期利益・人件費抑制 | 長期的な価値創造、ステークホルダー視点 |
人的資本経営を採ることで、社員のモチベーション・定着率・スキル向上を通じて、企業の持続可能性や競争力を高めることが期待されます。
なぜ今「人的資本経営」が求められているのか

ここでは、人的資本経営が注目されている背景について解説していきます。
無形資産の拡大
現代の企業価値は、モノ・設備といった有形資産よりも、知的財産、ブランド、組織能力、人的資本など無形資産に由来する部分の比重が大きくなってきています。人的資本はその中核要素と捉えられます。
労働人口の減少と人材獲得競争の激化
少子高齢化が進む中、労働人口は年々減少しています。優秀な人材を採用・定着させることはますます困難になっており、「人材の質」が企業の競争力を左右する時代になりました。
資本市場・投資家の要請の高まり
企業の持続可能性や将来性を判断する上で、財務指標だけでなく非財務指標(人的資本、気候変動対応、多様性など)の情報が求められるようになっています。
国際的な情報開示の潮流
米国ではSEC(証券取引委員会)が人的資本開示を義務化し、EUでも「CSRD(企業サステナビリティ報告指令)」が導入されています。日本でも内閣官房による「人的資本可視化指針(2022年)」が策定され、投資家が「人材への投資」を評価する時代に入りました。
このような背景から、人的資本経営は単なる人事の一分野ではなく、経営戦略として統合されるべきテーマと見なされるようになっています。
日本における制度やルール
人的資本経営そのものを直接定めた法律は現時点では存在しませんが、関連して「人的資本に関する情報開示」「開示義務化」といった制度・法令改正が進んでいます。以下に主な制度について解説していきます。
人的資本可視化指針
2022年8月、内閣官房の「非財務情報可視化研究会」が「人的資本可視化指針」を公表しました。これは、人的資本の情報開示の在り方を整理し、企業に対する手引きとして位置づけられています。
この指針は必ずしも法的拘束力を持つものではなく、あくまで「手引き/ガイドライン」としての位置づけです。
指針では、人的資本を可視化する際のステップ、考え方、情報開示の方向性、開示すべき7分野19項目などが整理されています。 19項目については、たとえば「人材育成」「従業員エンゲージメント」「流動性(離職・定着)」 「多様性」「健康・安全」「労働慣行」「コンプライアンス」などが挙げられています。 (参考:人的資本可視化指針 | 内閣官房)
有価証券報告書での人的資本開示義務化
2023年1月31日に、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正され、2023年3月期(以降)決算の有価証券報告書において、人的資本に関する情報の記載が一定程度義務づけられるようになりました。 義務化の対象範囲は上場企業など、有価証券報告書提出義務のある企業です。
義務化された開示欄は主に以下の2つです。
- 「従業員の状況」欄:新たに「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「労働者の賃金の男女間差異」の3指標の記載が義務化。
- 「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄:人的資本戦略に関する方針、指標、目標、進捗実績などを記載する必要。特に、「人材育成方針」「社内環境整備方針」が戦略として必須とされ、「指標および目標」の開示も義務化。
また、従来から法律で義務づけられていた制度(例:女性活躍推進法、育児・介護休業法)に基づく情報開示(女性管理職比率、育児休業取得率など)も、この義務開示範囲に含まれています。(参考:サステナビリティ情報の記載欄の新設等の改正について | 金融庁)
開示義務以外の関連制度・要請
上場企業に対しては、コーポレートガバナンス・コード改訂を通じて人的資本に関する情報開示が求められるようになっています。
ただし、義務化された情報開示の範囲は限定的であり、企業は自社特有の人的資本指標を任意開示で補完することが期待されています。 開示にあたっては、虚偽記載や過度な宣伝的表現を避ける必要があるため、法務・労務の調整、数値計測の信頼性確保、説明責任を果たす開示設計が重要となります。
人的資本経営の具体的な実践方法

人的資本経営を実践するためには、漠然と「人を大事にする」という観念だけでなく、戦略→計画→実行→検証という流れの中で「人的資本を投資対象として最大化する仕組み」を構築することが求められます。以下に、具体的なアプローチ方法とその手順を解説していきます。
ステップ1:現状把握と課題分析
人的資本経営を有効にするには、人的資本施策が単なる「人事の仕事」ではなく、企業のコアな経営課題と直結していなければなりません。つまり、
- この会社が今・将来何をなすべきか
- そのためにどのような人材・スキル・組織が必要か
という視点で、人的資本戦略を策定することが出発点となるのです。
<具体的なやり方例>
- 経営計画・中期経営計画から、キー戦略や成長領域を抽出する
- その戦略実現に必要な人的リソース(スキル、人数、配置)を逆算する
- “人的資本ポートフォリオ”を設計する(コア人材、支援人材、将来人材などの分類)
- 各事業部門や現場と議論し、人材ニーズをすり合わせておく
ステップ2:目標と現状のギャップの可視化
目標を設定しても、現状がどこにあるか見えなければ、どこを・どれだけ改善すべきかが曖昧になってしまいます。そこで、現状をできるだけデータで可視化することが不可欠です。
<具体的なやり方例>
- 現状データを収集する(定着率・離職率・採用成功率・従業員満足度・社員エンゲージメント・研修投資額と成果・スキルマップなど)
- 人的資本可視化指針などを参考に、自社で着目すべき指標を洗い出す
- 過去推移データやベンチマーク(業界他社・先進企業)との比較データを集める
ステップ3:KPI・目標設定
目標達成までの道筋を明らかにするため、「いつまでに何をどこまで達成するか」を定量化された指標で示す必要があります。
<具体的なやり方例>
- 定量的KPIを選定する(例:離職率を○年間で○%に引き下げる、社員満足度スコアを○点まで向上させる、研修受講率を○% にする、業務部署別スキル充足率を○%にするなど)
- 補助指標もあわせて設計する(例:中間指標として研修参加率、内部異動率、昇格率、社内公募率など)
- KPIに対して「目標」「基準」「アクションプラン」との対応関係を明確にする
- 指標の達成時期やモニタリング頻度(年次、四半期、月次など)を設計する
- KPIは、戦略上インパクトのある指標であること、かつ実行可能性や因果関係を意識して選定する
ステップ4:施策設計・実行
Step2で可視化したギャップを埋めるべく、具体的な施策(制度、オペレーション、文化づくりなど)を設計・実行し、人的資本を鍛えていくフェーズです。
| 領域 | 施策例 |
|---|---|
| 採用・配置 | 戦略人材の獲得、ダイレクトリクルーティング、社内公募制度、配置ローテーション、適材適所配置 |
| 育成・教育 | リスキリング研修、OJT/Off-JT、メンター制度、エキスパート制度、eラーニング、キャリアデザイン支援 |
| 評価・報酬制度 | 成果主義、人事評価基準の見直し、OKRとの連動、報酬体系の透明化、インセンティブ制度 |
| 働き方・環境 | フレックスタイム、リモートワーク、時短勤務、ワークライフバランス支援、健康経営、ウェルビーイング施策 |
| ダイバーシティ/インクルージョン | 女性活躍推進、障がい者雇用、外国人採用、LGBTQ対応、役割モデル、制度的支援 |
| エンゲージメント施策 | 社員サーベイ、1on1制度、風通し改革、社内コミュニケーション強化、社内承認制度 |
| 人事データ基盤情報活用 | タレントマネジメントシステム(TMS)、人事ダッシュボード、人材データの可視化と分析基盤構築 |
人的資本経営を定着させるには、これら施策を単発で行うだけでなく、人事制度(評価・報酬・育成・異動)と設計的に連動させることが重要です。たとえば、どのような行動・価値観を促したいかを評価基準に入れる、育成制度をKPIと紐づけるなどの設計が求められます。
ステップ5:効果検証・改善・開示
せっかく施策を実行しても、効果がわからなければ改善できずに終わってしまいます。検証と改善を回す仕組みを定着させ、さらに外部への発信も進めていく必要があります。
<具体的なやり方例>
- KPI実績とのギャップを定期モニタリングする(四半期/年次など)
- 施策ごとの効果(因果関係)を定量・定性で分析する
- 成果が出ていない施策については原因分析を行い、再設計または撤退判断する
- 成功事例・改善事例を横展開する
- 各ステークホルダー(従業員、投資家、求職者、取引先等)に向けて人的資本経営の方針・成果・目標を開示・発信する(たとえば、有価証券報告書や統合報告書での人的資本情報開示)
- 社内レビュー(KPIレビュー、改善会議)を定例化し、ガバナンスを強める
リーダーに求められる視点
人的資本経営をうまく進めるには、経営者として抑えるべきポイントがあります。以下に、そのポイントについて解説していきます。
- 経営トップのコミットメント:人的資本経営を“向こう側の仕事”ではなく、リーダーが旗振りをすることが大切です。
- 現場巻き込み・ボトムアップとのバランス:現場管理者や社員を設計段階から関与させ、「自分ごと感」を持たせることで定着を促すことができます。
- まずは小さな成果を出す:最初から大がかり・完璧を目指すのではなく、小規模施策で効果を出し、信頼を築きつつ拡張するアプローチが現実的であり、モチベーション維持につながります。
- データ基盤と情報整備:スムーズな実行や検証のため、データを取得できる基盤やツール(人事システム、データベース、可視化ツールなど)を整える必要があります。
- 因果関係を意識した設計:施策→KPI→成果という因果構造を意識して設計しないと、実効性が薄くなってしまいます。
- 改善サイクル(PDCA)の徹底:施策をやって終わりにせず、定期的にレビュー・改善・再設計を行う仕組みを前提にすることが大切です。
- 開示・発信の整合性:外部ステークホルダーへの開示・説明責任を意識し、虚偽表現とならないよう、透明性・整合性を重視した表現にすることが求められます。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、人的資本経営について、その概要や重要性、実践のステップ、経営者やるべきことなどについて解説してきました。
まとめると、
- 人的資本経営は、企業が「人材」を単なるコストではなく投資対象と捉え、戦略的に活用する経営アプローチ手法である
- 企業価値の無形資産化、ESG投資拡大、資本市場の変化などを背景に、その重要性が高まっている
- 日本では、法制度として直接的な「人的資本経営法」はないが、開示制度が導入され、さらに「人的資本可視化指針」が企業の手引きとして整備されている
- 具体的なアプローチ方法は①現状把握と課題分析、②目標と現状のギャップの可視化、③目標の設定、④ギャップを埋める施策の設計・実行、⑤効果検証・改善・開示
- リーダーとして、自ら旗振りをして戦略にコミットし、緻密に設計し、改善サイクルを徹底することが大切
以上が本記事の要点となります。
企業の持続的成長を支えるのは設備でも資金でもなく、「人」です。人的資本経営は一過性のブームではなく、未来の企業競争力を左右する根幹戦略です。経営者自身が率先して「人を活かす経営」に舵を切り、企業と従業員が共に成長する仕組みを築くことが、次の時代を生き抜く鍵となるでしょう。
本記事が、人的資本経営の知識を深める一助となれば幸いです。
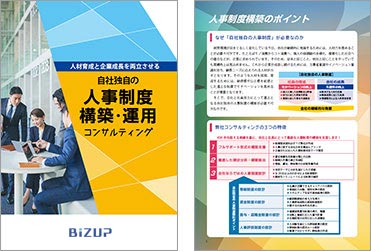 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。