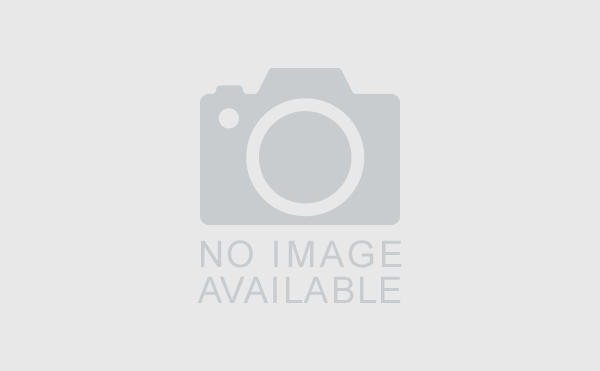昇給月の決め方は?他社事例と退職金制度への影響も解説

昇給月をどのように設定するかは、企業の人事戦略に直結する重要なテーマです。人件費管理の安定性や社員のモチベーション、さらには制度全体の透明性に影響を及ぼすからです。特に中堅企業では、昇給を「全社員一律に行うべきか」「個人ごとに評価基準と連動させるべきか」という判断に悩むケースが多いでしょう。加えて退職金制度と連動させる必要があるため、昇給のタイミングを軽視すると長期的な人件費最適化が困難になるのです。本記事では、昇給月の代表的な決め方、他社事例やトレンド、そして退職金制度との関連性について解説し、実務に役立つポイントを紹介していきます。
目次

昇給月の主なパターンとメリット・デメリット

昇給月をどのように設定するかは、制度設計の根幹です。代表的なパターンは「全社一律型」「評価連動型」「個別調整型」の3つに分けられます。
全社一律型
全社員を同じ月に昇給させる方式です。日本企業で最も一般的であり、人件費管理や制度説明がしやすい点が特徴といえるでしょう。一方で、個々の成果と昇給が必ずしもリンクしないため、社員によっては納得感に欠ける可能性があります。さらに、業績が低迷している時期でも一律昇給を行う必要があるため、経営側にとって柔軟性に欠ける場面が出てくるのも実情です。
評価連動型
社員の人事評価に基づき、昇給月を決める方式です。成果に応じた報酬が得られるため、モチベーションの向上につながりやすいでしょう。ただし評価制度が不透明だと「恣意的」と受け止められるリスクが伴います。また、評価者のスキルや基準の明確さによっては不公平感を招きやすく、制度運用に高度な仕組みと研修が不可欠になるのが特徴です。
個別調整型
職種や採用時期に応じて昇給月を個別に設定する方式です。柔軟性は高いですが、管理が煩雑になりやすいのがデメリットです。特に中堅規模の企業では運用負荷が問題になりやすいといえるでしょう。さらに、管理が属人化すると公平性に疑念が生じ、社員同士の間に不満や不信感を生むリスクも見逃せません。このように、昇給月の決め方は一長一短であり、どの方式を採用するかは企業の戦略や人材ポートフォリオに大きく依存します。
他社の昇給月設定トレンド
昨今の企業動向を見ると、従来の「一律型」から徐々に変化が見られます。特に人材の多様化が進む中で、柔軟な制度設計を採用する企業が増えているのです。
ここでは代表的な3つの傾向を紹介し、それぞれの特徴を整理します。
| 方式 | 特徴 | 課題 |
|---|---|---|
| 全社一律型 | 管理が簡単で制度説明が容易 | 成果反映が弱く不満につながる |
| 評価連動型 | 成果主義に沿った処遇が可能 | 評価制度が不透明だと不信感が高まる |
| 個別調整型 | 柔軟性があり採用多様化に対応 | 管理が複雑化し負担が大きい |
最近では「基本は全社一律だが、特定職種や成果型ポジションに限り評価連動を導入する」といったハイブリッド型が増加しています。これにより人件費の安定性とモチベーション向上の両立を図ろうとする動きが見られるのです。さらに、退職金制度とのバランスを重視する企業も多く、単に「いつ昇給するか」だけでなく「長期的なコスト設計」として制度をとらえる姿勢が広がってきています。
昇給制度と退職金制度の連動方法
昇給制度と退職金制度は独立した仕組みのように見えて、実際には深く結びついています。基本給が変動すれば、その先にある退職金額や人件費計画に直結するためです。設計の段階から両制度を一体で考えることで、企業にとっても社員にとっても納得感の高い仕組みを実現できるでしょう。ここでは、代表的な連動のポイントを整理します。
最終給与方式におけるリスク管理
退職金の算定を「最終給与方式」で行っている企業では、昇給のタイミングが退職金総額を大きく左右します。例えば定年直前に大幅昇給を実施した場合、長年の勤務実績よりも直近の昇給が過度に反映されてしまうのです。これは予想外の人件費増加につながり、経営に負担を残す可能性があります。そのため、制度設計段階から昇給のルールを明確に定め、定年前の昇給率を調整するなどの工夫が求められます。
ポイント方式・定額方式との整合性
一方で「ポイント方式」や「定額方式」を採用する企業では、昇給が必ずしも退職金額に直結しません。しかしながら、昇給ルールが不透明だと社員から「処遇全体の公平性が見えにくい」と捉えられるリスクがあります。退職金制度そのものは安定的でも、昇給の仕組みが理解されなければ納得感は薄れてしまうのです。したがって、両制度を別個のものとして運用するのではなく、説明資料や研修を通じて「両者がどのように関連するか」を明示することが効果的といえるでしょう。
長期的なコストと制度改正への対応
さらに注意すべきは、法制度や会計基準の改正に伴う影響です。退職給付会計や企業年金制度の見直しは定期的に行われており、昇給の設計を見直さないままでは不整合が発生する恐れがあります。人件費の長期予測を行い、複数シナリオで昇給と退職金を同時にシミュレーションすることで、将来の負担を可視化できます。これにより、短期的な社員の満足度と長期的な財務健全性を両立できるのです。
昇給制度設計を成功させるポイント
昇給制度を円滑に運用するには、単にルールを決めるだけでは不十分です。制度を機能させるためには、運用上のポイントを押さえることが欠かせません。
社員への説明責任を果たす
制度の透明性を担保するためには「なぜこの方式を選んだのか」を丁寧に説明することが必要です。説明不足は社員の不信感を招き、せっかくの制度も形骸化してしまうでしょう。また、昇給がどのように将来の退職金やキャリアに影響するのかもあわせて示すことで、納得度をさらに高めることができます。
他社との比較データを活用する
自社に合う方式を選定するには、同業他社や業界全体の傾向を参考にすることが効果的です。データをもとにした検討は、経営層への説得材料にもなるのです。さらに、社内での議論を進める際に「主観ではなく客観的データに基づいた判断」と位置づけられるため、関係部門の合意形成がスムーズになる効果も期待できます。
長期的な人件費シミュレーションを行う
昇給と退職金を切り離さずにシミュレーションすることで、将来の人件費負担を予測できます。これにより、短期的な納得感と長期的な持続性の両立が可能になるのです。加えて、経営環境が変化した場合にどの程度の柔軟性を持たせるべきか、複数シナリオで検討できる点も大きなメリットといえるでしょう。
ビズアップ人事コンサルの無料相談紹介

昇給制度の検討においては、専門家の知見を取り入れることも重要です。特に中堅企業では社内リソースに限界があるため、人事制度設計の外部支援を活用することで効率的に課題を解決できます。
ビズアップの人事コンサルサービスでは、昇給制度や退職金制度を含む人事制度全般について、無料のお見積もり相談を受け付けています。制度設計の初期段階から、既存制度の見直しまで幅広く対応しているため「どこから手をつければいいのか分からない」という企業にとって心強い存在となるでしょう。外部視点を取り入れることで、社内だけでは見逃していた課題に気づける可能性も高まります。
まとめ
昇給月の決め方は単なる事務的な日程調整ではなく、企業の人事戦略全体に影響を与える要素です。全社一律型、評価連動型、個別調整型のいずれを選ぶにせよ、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で判断する必要があります。さらに、退職金制度との連動を視野に入れた長期的な設計を行うことで、社員の納得感と経営の持続性を両立できるのです。
制度設計に不安を感じる場合は、必要に応じて専門家の支援を取り入れることで、自社に最適な昇給制度をより確実に構築できるでしょう。
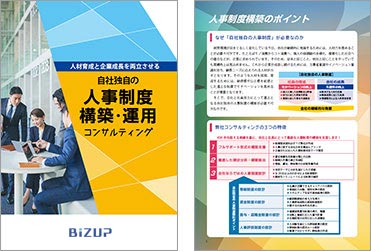 経営者・人事部門のための
経営者・人事部門のための
人事関連
お役立ち資料
資料内容
-
制度設計を“経営インフラ”として機能させる仕組みと、組織力向上・人件費最適化を同時に実現するプロフェッショナルのアプローチを詳しくご紹介。「人事制度構築システム」「構築・運用コンサルティング」にご関心のある方は、ぜひご覧ください。